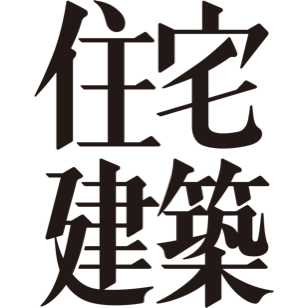
【12月号書評】『柿沼守利作品集 Schri Kakinuma』(柿沼守利 著/建築資料研究社)

『柿沼守利作品集 Schri Kakinuma』
柿沼守利 著
建築資料研究社/2025年/264頁/A4判/9,460円(税込)
柿沼守利の言葉
評者:井上洋介(建築家)
建築家柿沼守利のことを初めて知ったのはいつ頃のことだろう。今から20年前の2005年頃、雑誌『コンフォルト』が何号かにわたり氏の住宅作品を丁寧に紹介していて、強く印象に残ったのを覚えている。和風の趣きをもった住宅の、素材の扱いに新鮮さを感じた。重厚な落ち着きのある作風のなかで、素材の取り合わせとディテールの扱いは、伝統に根ざしていながら、現代的であり、独自の感性が感じられ、他の建築にはない豊かさを感じたことを思い出す。
プロフィールには、1943年東京生まれ。68年より白井晟一に師事、83年氏の逝去に伴い翌年に独立、とそれしか記されていなかった。白井晟一の弟子なのかと、とても興味がわいた。それにしても師と同じで、どこか謎めいていた。
ひたすら柿沼守利と白井晟一の建築を見て、白井晟一から柿沼守利に流れているもの、いないもの、そのありかを探っていくような旅であった。
有田のチャイナ・オン・ザ・パークは、白井晟一の影響が確かにあるのだけれど、それはどこか薄まり、白井の建築に感じる独特の臭みのようなものがとれていて、自分としてはむしろ心地良いものに感じられた。白井晟一の影響の他に、スカルパやミースの影が感じられ、それが一つの柿沼守利の建築作品として結実していた。建築家同士の、リレーのバトンと言ったらいいのだろうか。自分も興味のあったスカルパや、あるいはカーンからの影響を目の当たりにして、建築を通して柿沼守利と対話をしているような、そんな時間であった。
今一度、自分なりにコンクリートの表現なるものについて見つめなおし、深く掘り下げてみたいと思うきっかけとなった作品である。
九州へ建築を見てきた話や、氏の建築から白井晟一やスカルパの影響をどう感じたかなど、恐れ多くも正直に本人に話をした。
柿沼さんは黙ってずっと聞いていた後、「スカルパはもちろん見ている、9回訪れている」と、さらっと答えられた。柿沼さんの発した、そのたった一言は、ガツンと頭を叩かれたような思いであった。自分では海外も含めてかなり建築を見ているつもりであった。好きな建築は作品によっては繰り返し訪れていたし、このくらい見ていればもう十分ではないかと、分かったつもりでいたような気がしていた。だが、道を究めている方というのは、ものを見ること一つとってみても、違うんだなと、思い知らされた。繰り返し見ることでようやく見えてくるものがあり、何かをしっかり受け継ごうとするなら、それ相応の覚悟と時間が必要だということも。
質問の時間、九州を同行したうちの事務所の所員が、湯布院の旅館「亀の井別荘」の改修工事の際、現場にはどのくらいの頻度で通っていたのかと聞くと、「ほとんど毎日現場にいた」とこれまたさらっと答えられた。その一言もまた、今でもずっと心に残る柿沼さんの言葉の一つである。
ご本人の話を聞くことのできる、ほんの少しの機会ではあったが、その話の数々をその後何度も思い返すこととなろうとは。そして今、こうして氏の作品集の書評を自分が書くことになろうとは。人生とは不思議なものである。
この本の巻頭には柿沼守利自身が書いた良寛の詩が納められている。現代語訳はご本人によるものなのだろうか。
私は 両足を伸ばして 独りを楽しんでいる
そして私が知る限り数少ない本人の書いた文章、あとがきを読む。
「師亡きあとのわが歩みを顧みれば、洵に慚入るばかりである。」(籬楓隻語)
「こうして拙作の羅列をみるにつけ、永きに亘って師の薫陶を受ける縁にめぐまれながらも仕事は萬分の壱にも満たず、何一つ体得できていなかったと、自省の念にかられる次第でございます。」(あとがき)
そして最後に陶淵明の詩で、作品集は締めくくられている。
人生実難
死如之何
嗚呼哀哉
それを読んでふと、晩年の白井晟一が自分の作品集の巻頭に書いていた書を思い出した。
そこに存在するであろう、渡された重たいバトンの中身とは?
井上洋介(いのうえ・ようすけ)
1966年 東京都に生まれる。1991年 京都大学工学部建築学科卒業。1991年~2000年 坂倉建築研究所勤務。2000年 井上洋介建築研究所設立。






