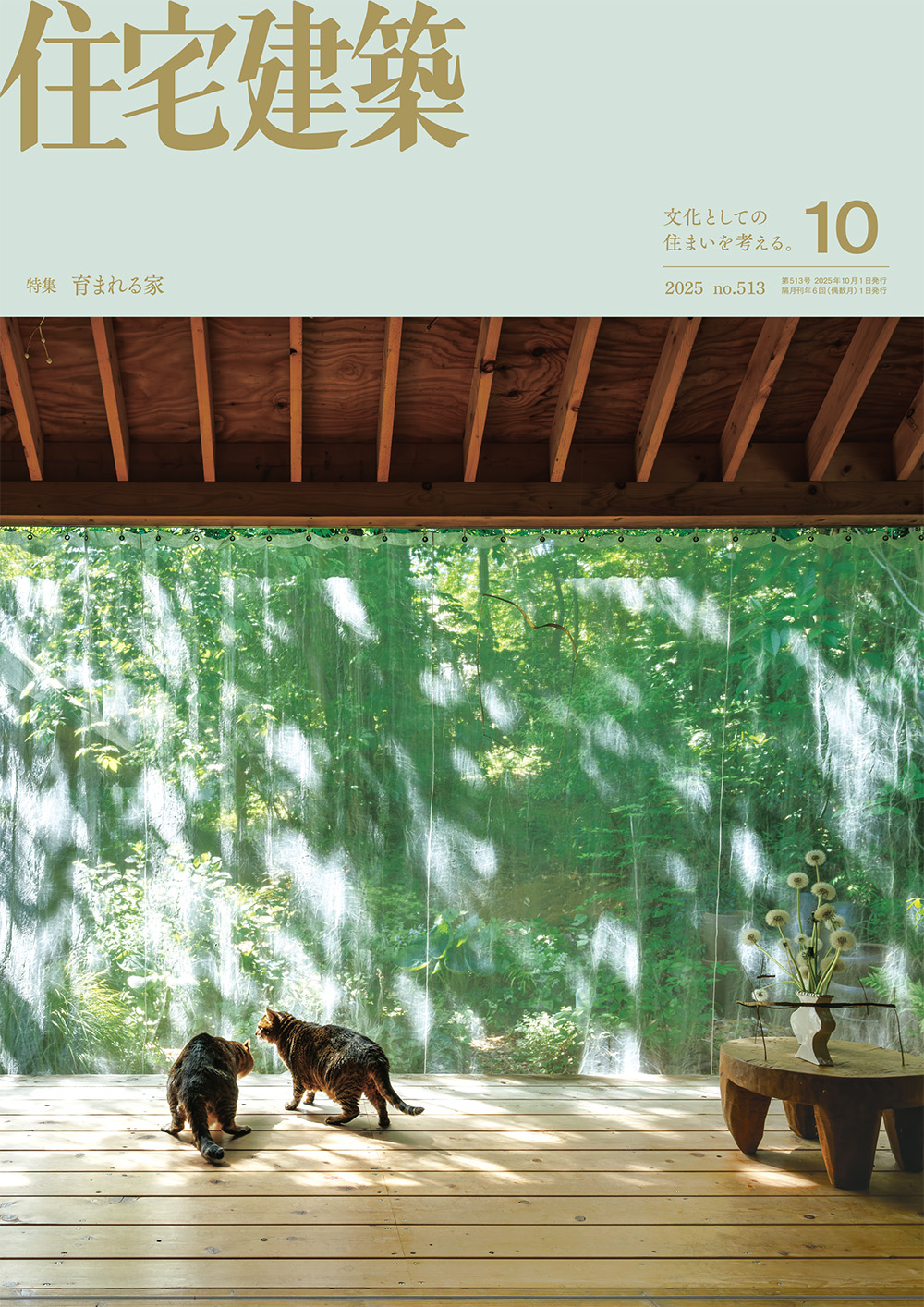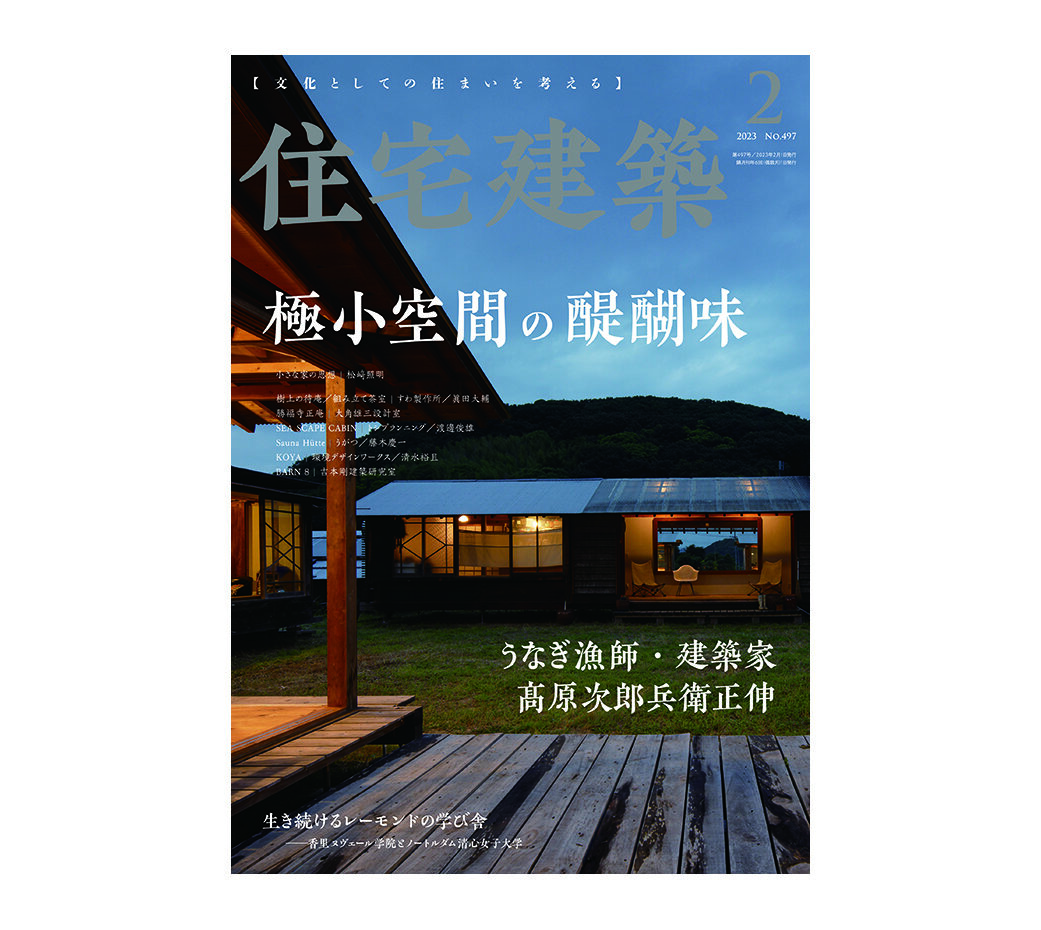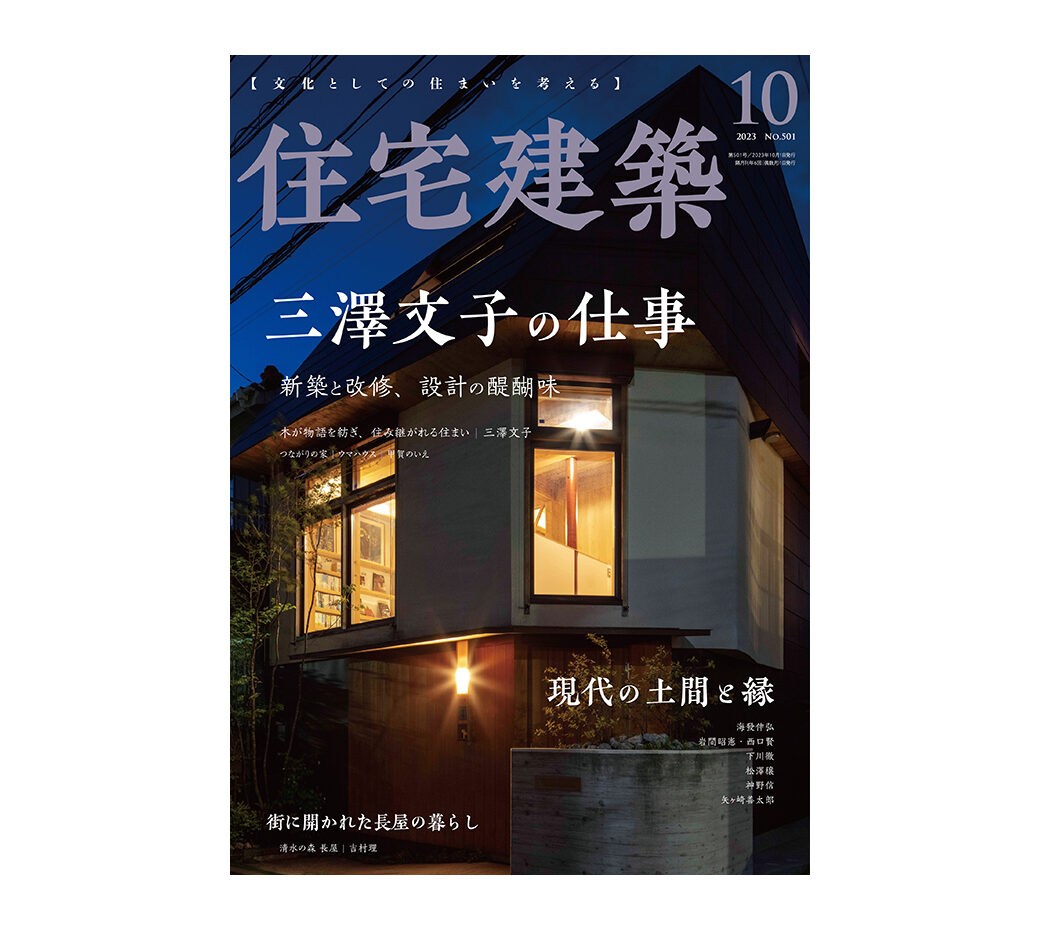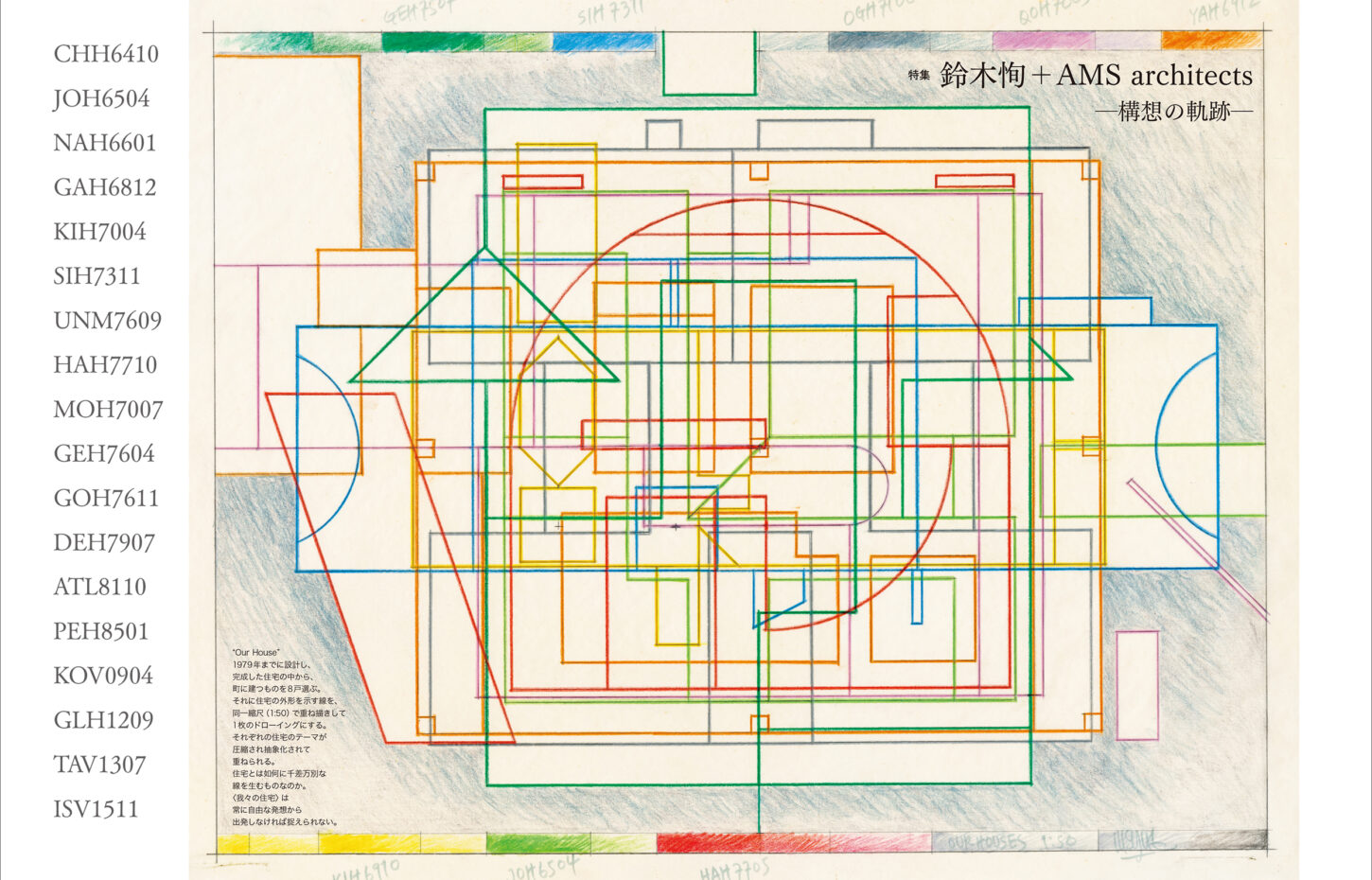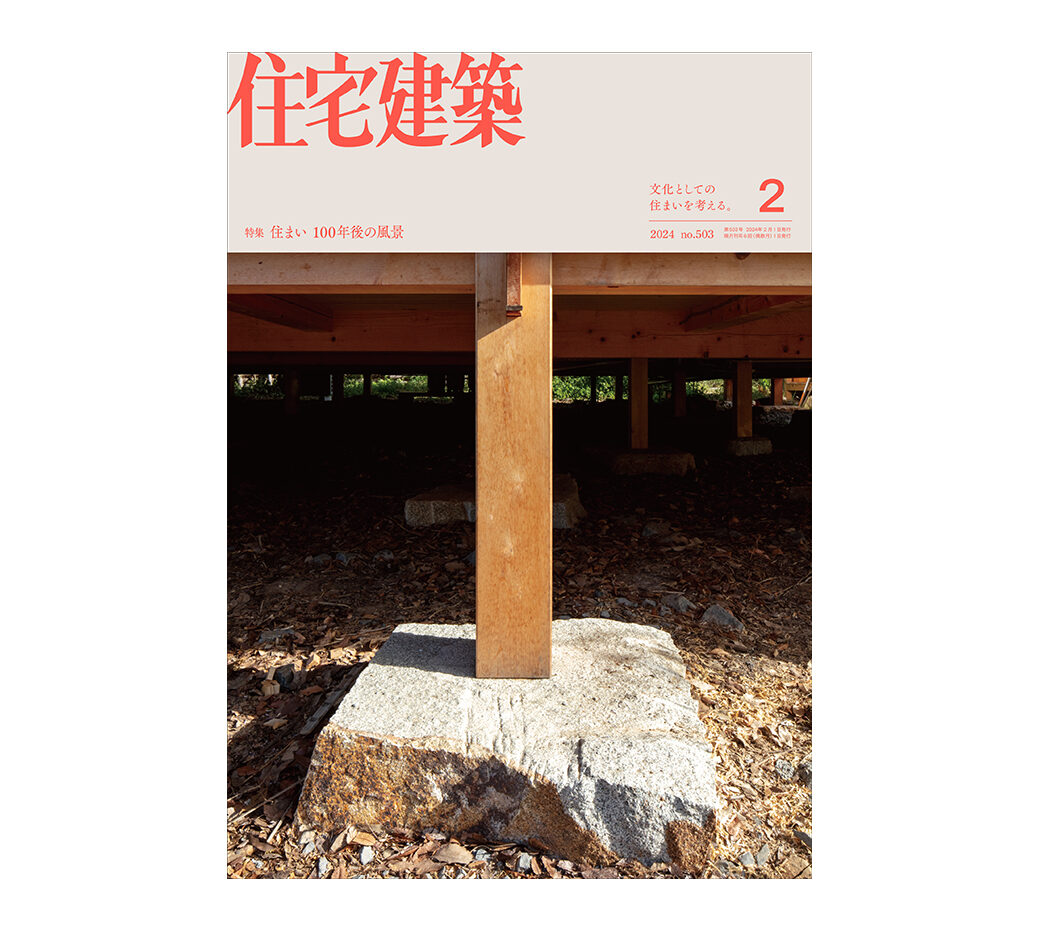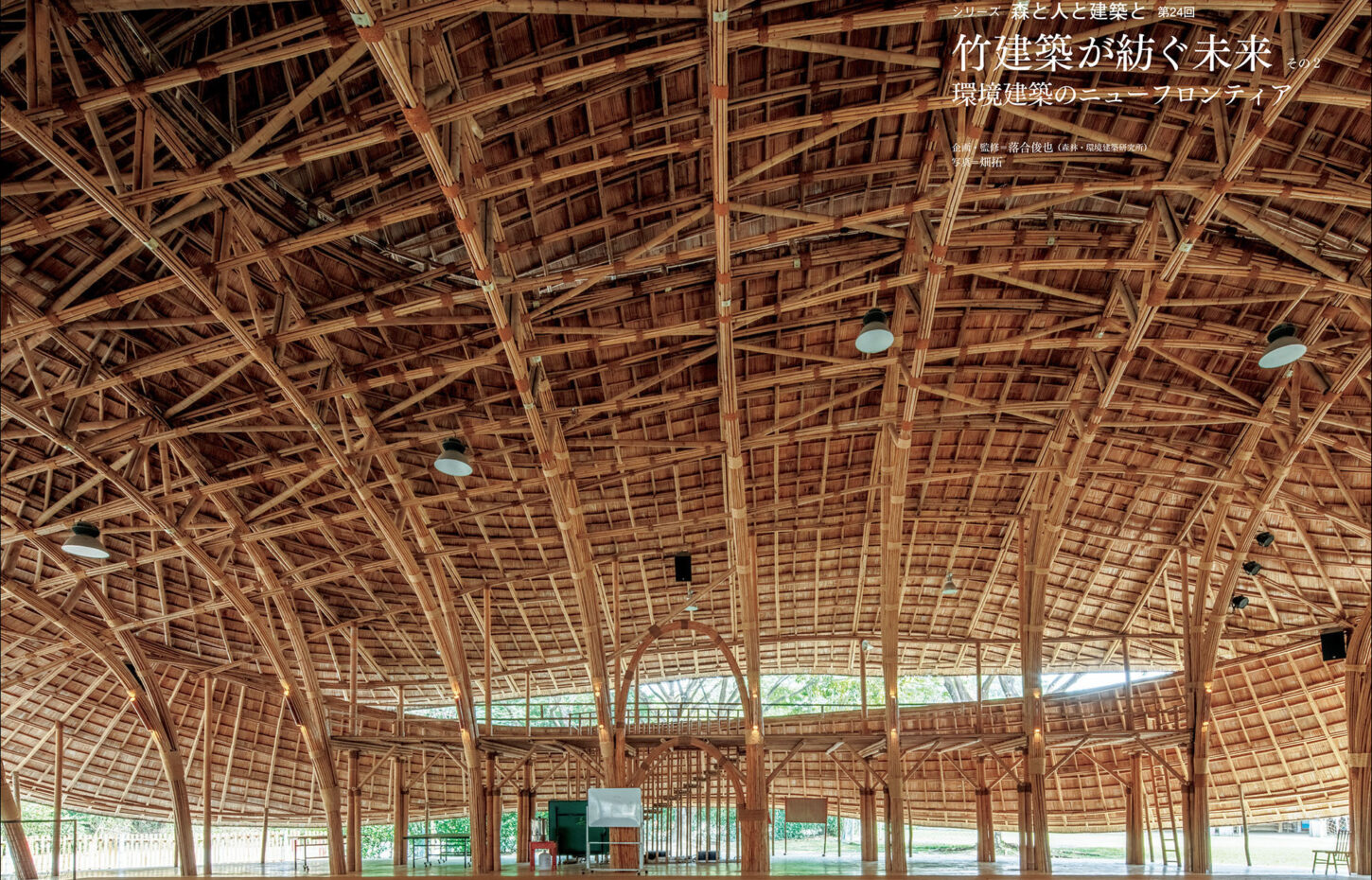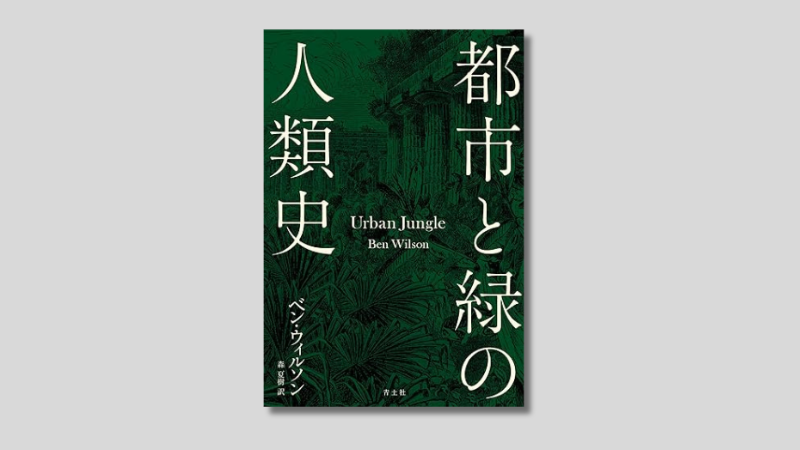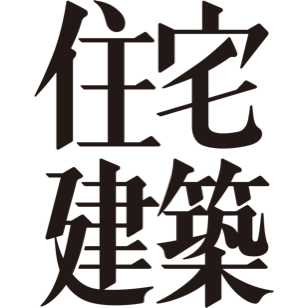
【10月号書評】『コミュニティデザインの現代史 まちづくりの仕事を巡る往復書簡』(饗庭伸、山崎亮 著/学芸出版社)
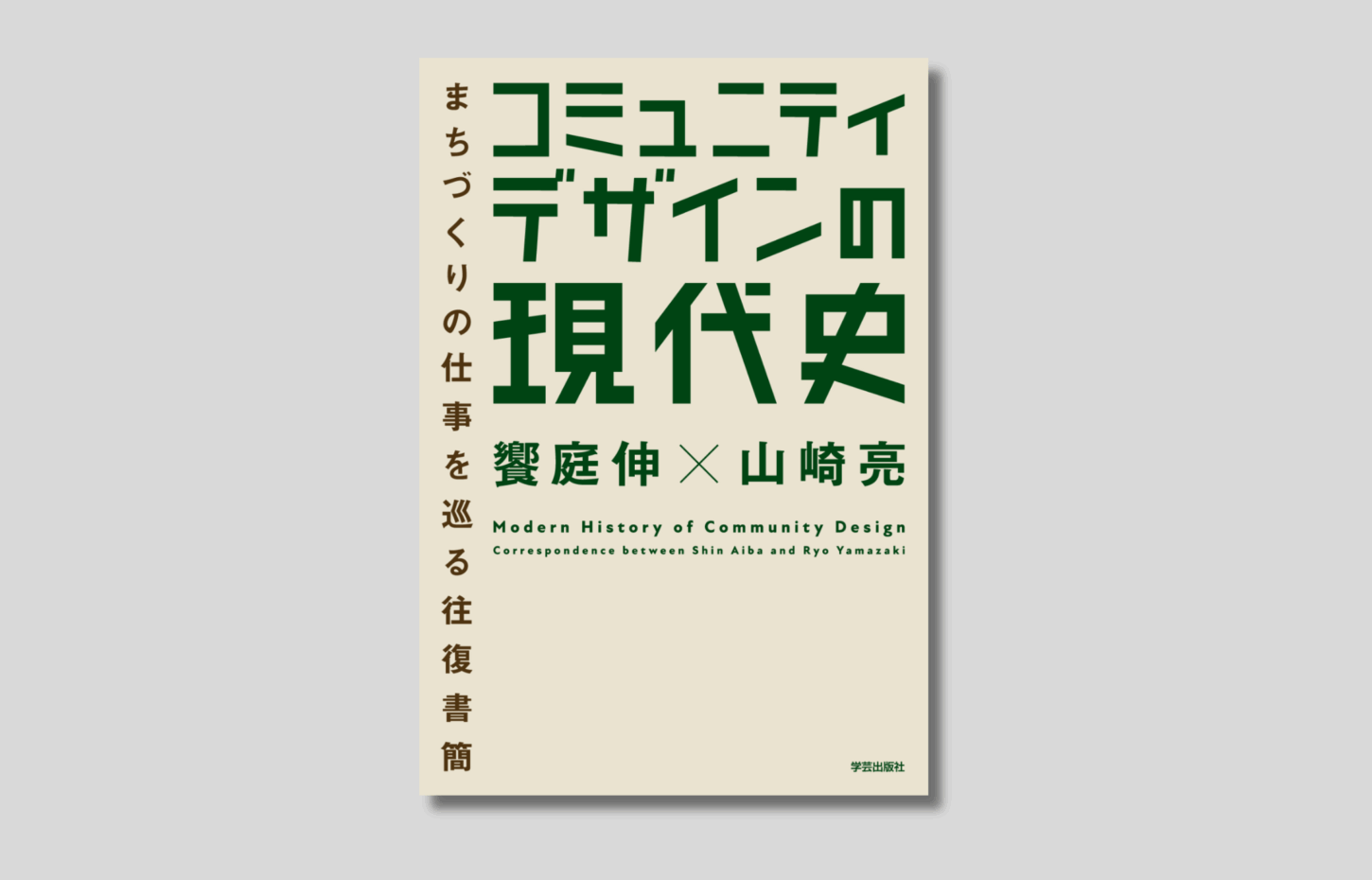
『コミュニティデザインの現代史 まちづくりの仕事を巡る往復書簡』
饗庭伸、山崎亮 著
学芸出版社/2024年/288頁/四六判/2,640円(税込)
コミュニティデザインの温故知新
評者:松村淳(社会学者)
本書は、都市計画を専門とする饗庭伸と、コミュニティデザイナーの山崎亮による共著である。
まちづくりやコミュニティデザイン、そしてその手法としてのワークショップが、すでに社会に広く浸透し、市民権を得たように見える現在において、こうした分野の第一線で活躍する2人が、先人たちの仕事を改めて見つめ直しながら、自らの経験や思索を交わし合い、コミュニティデザインを再考する本書は、まさに今の時代にふさわしい1冊と言える。
本書は、饗庭と山崎の2人による往復書簡というスタイルをとっている。2人の間の往復書簡は、日本がコロナ禍に見舞われはじめた2020年の春に始まり、その年の冬に終わるまで、計22回のやりとりが交わされた。
本書の目的は、ひとことで言えば、コミュニティデザインの歴史を辿ることである。その背景には、「コミュニティデザイン」や「まちづくり」という言葉が今ではすっかり人口に膾炙しているものの、それらがいつ、どのように日本に根づき、発展していったのかについては、あまり顧みられることなく、「読み人知らず」のようになっているという両者の問題意識がある。
さて、本書の章立てを見てみよう。本書は、冒頭の「参加型まちづくりパイオニアたちの見取り図」と、8章立ての本章から成っている。それぞれの章には基本的に2人の書簡が1本ずつ掲載されている。8章の中に22本の書簡が掲載されており、通し番号が振られている。どちらかの書簡が先に掲載され、後半はそれに対する応答である。まずは章立てに基づいて本書の中身を見ていきたい。
第1章では、往復書簡を交わすきっかけとなった出来事が山崎によって語られる。その後、饗庭の応答が続く。饗庭は兵庫県西宮市で育ち、市民に向けて配布されている『宮っ子』という冊子でコミュニティを知ったという。山崎も小学生時代に西宮市に住んでいたという共通点にも触れられているが、この書評を書いている筆者も、学生時代から現在に至るまで西宮市に在住しており、親近感を禁じ得ない。
第2章では、まちづくりのパイオニアたちの話題を山崎が膨らませ、その返信で饗庭がパイオニアたちの見取り図やインタビューの技法を示している。2章の終わりには林泰義へのインタビューが掲載されている。
第3章は、山崎による林のインタビューへの感想と、当時のまちづくりをめぐる素描が記される。それに対する返信として、饗庭によって林の仕事が整理される。さらにそれに対する返信として、山崎はアメリカのコミュニティデザインの源流を詳細に振り返るのである。
第4章では、饗庭が神戸市長田区真野地区のまちづくりをテーマに語っている。アソシエーションデザインが主流のなかで、真野地区という特定の空間に焦点を当てたまちづくりが、誰によって、どのようにデザインされ、実行されてきたのかについて詳細に語られている。山崎によるリプライを経て、真野地区のまちづくりに詳しい乾亨のインタビューへと繋がる。
第5章では、コミュニティ計画をめぐる3つの論点、すなわち「空間と計画」「組織」「手続き」について、さまざまな観点から検討されている。とりわけ、哲学者の國分功一郎の中動態概念を、まちづくりにおいて人々を動員していくロジックの検討のための補助線として効果的に引用しており、非常に見通しがよくなっている。山崎のリプライもそれに触れつつ、能動態のまちづくりをいかに進めるのがよいのかについての逡巡が語られ、神戸のまちづくりを長年担ってきた小林郁雄のインタビューへと繋がる。
第6章では、まちづくり事務所の経営がテーマである。1970年代前後に民間の都市計画事務所が設立され、それは研究者が仕事を請けていくなかで徐々に組織化されていったものの、経営的なことは誰もやりたがらなかったということが語られている。山崎も自身の会社であるStudio-Lを立ち上げたいきさつ、なぜNPOにせず会社組織にしたのか、といった思いが語られ、山崎が尊敬しているという浅海義治のインタビューへと繋がる。
第7章では、浅海がインタビューの中で述べていた、コミュニカティブ・プランニング、アドボカティブ・プランニング、ストラテジック・プランニングという3つのプランニングについて、2人がそれぞれ話題を展開する。
第8章は、第7章の問題意識が引き継がれ、「誰のために、何のためにワークショップをするのか」といった根源的な問いに回帰し、「人が育つためにやる」「偏りがあってもいいので、無理にまとめる方向に持っていかない」といった、あるべき方向性が示されている。
以上、本書の概要を各章のトピックに触れながら簡単に素描してみた。ここからは、筆者が本書を読んで関心を抱いたことについて論じてみたい。
饗庭は「1970年代頃のコミュニティ計画の周辺では、コミュニティが王道、アソシエーションはどちらかというと邪道なものとして考えられていた」(75頁)と述べている。そして、そうした傾向は今も続いており、現代ではアソシエーションが優っていると述べている。
アソシエーションは、必ずしも特定の地域や場所に基盤を置くものではない。それはサークル活動や住民運動、1990年代後半以降はNPOとして結実していくものである。確かに、特定の地域を盛り上げていこうとするまちづくりやコミュニティデザインの観点から見れば、必ずしも地理的近接性に依らないアソシエーションは歓迎されなかったということには納得がいく。
本書のなかで、山崎がコミュニティデザインの仕事を始めた当初、先輩たちから「コミュニティをどう定義するのか」という質問がよく投げかけられたと述懐している。その質問に対して山崎は、的確に答えることができず、「人それぞれじゃないですかね」という曖昧な答えを返すのが精一杯であったという。これは山崎が未熟であったからではない。山崎はコミュニティを定義することへの違和感をもっていたのだ。
山崎の上の世代が考えるコミュニティは、小学校校区くらいの空間的な広がりを指していた。そして彼らは、コミュニティの専門家として外部からコミュニティをデザインしようとした。しかし山崎は、そうした態度に違和感を覚えていたと語っている。山崎は「自分は誰とどう生きていくのかを話し合ったり、活動を生み出したりして、充実した豊かな生活を実現させることが重要だと考えていた」(93頁)と述べている。
高度経済成長の時代にあっては、都市計画の主眼は、限られた空間にどのように効率的に人口を配置していくのかという課題に応えることであった。まちづくりやコミュニティデザインは、効率性だけではなく、そこに暮らす人々を主体に据え、彼らの幸福度を高めるためのデザインに取り組んだ。こうした目的を達成するいちばんの方法は、住民を参加させることである。そうして住民参加型の制度設計が試行錯誤されはじめ、ワークショップなどさまざまな手法が編み出されたのである。
しかし、「コミュニティを定義する」という行為は、ともすればそうした試みをあらかじめ設定されたゴールに誘導してしまう危険性も孕んでいる。これは、山崎が考えるコミュニティデザインの理想とは大きくかけ離れてしまうものであったのだ。
評者は、本書を読むまで、ワークショップを、あらかじめ設定された青写真を市民に認めさせるために巧妙に設計されたツールであると考えていた。しかし、本書を読めば、そうした認識が誤りであったことに気がつく。
ファシリテーターは、市民から出てくる多様な意見を否定せず受けとめ、個性を徹底して尊重することで、主体的に参加する市民を育成しているのである。
本書はコミュニティデザインに留まらず、成熟した市民社会のあり方について思索を深めるためにも示唆に富む一冊である。
松村淳(まつむら・じゅん)
香川県高松市に生まれる。1998年 関西学院大学社会学部卒業。2004年 京都造形芸術大学芸術学部建築デザインコース卒業。設計事務所勤務等を経て、2011年 関西学院大学大学院社会学研究科入学。2014年 同大学大学院社会学研究科博士後期課程単位取得満期退学。博士(社会学)。二級建築士。専門社会調査士。2024年〜 神戸学院大学人文学部講師。専攻は、労働社会学、都市社会学であるが、近年は建築社会学の可能性について取り組む。『建築家として生きる―職業としての建築家の社会学』(晃洋書房)で、2022年 日本労働社会学会奨励賞、2025年 日本建築学会著作賞を受賞。そのほかに『建築家の解体』(筑摩書房)、『愛されるコモンズを生きる―街場の建築家の挑戦』(晃洋書房)がある。