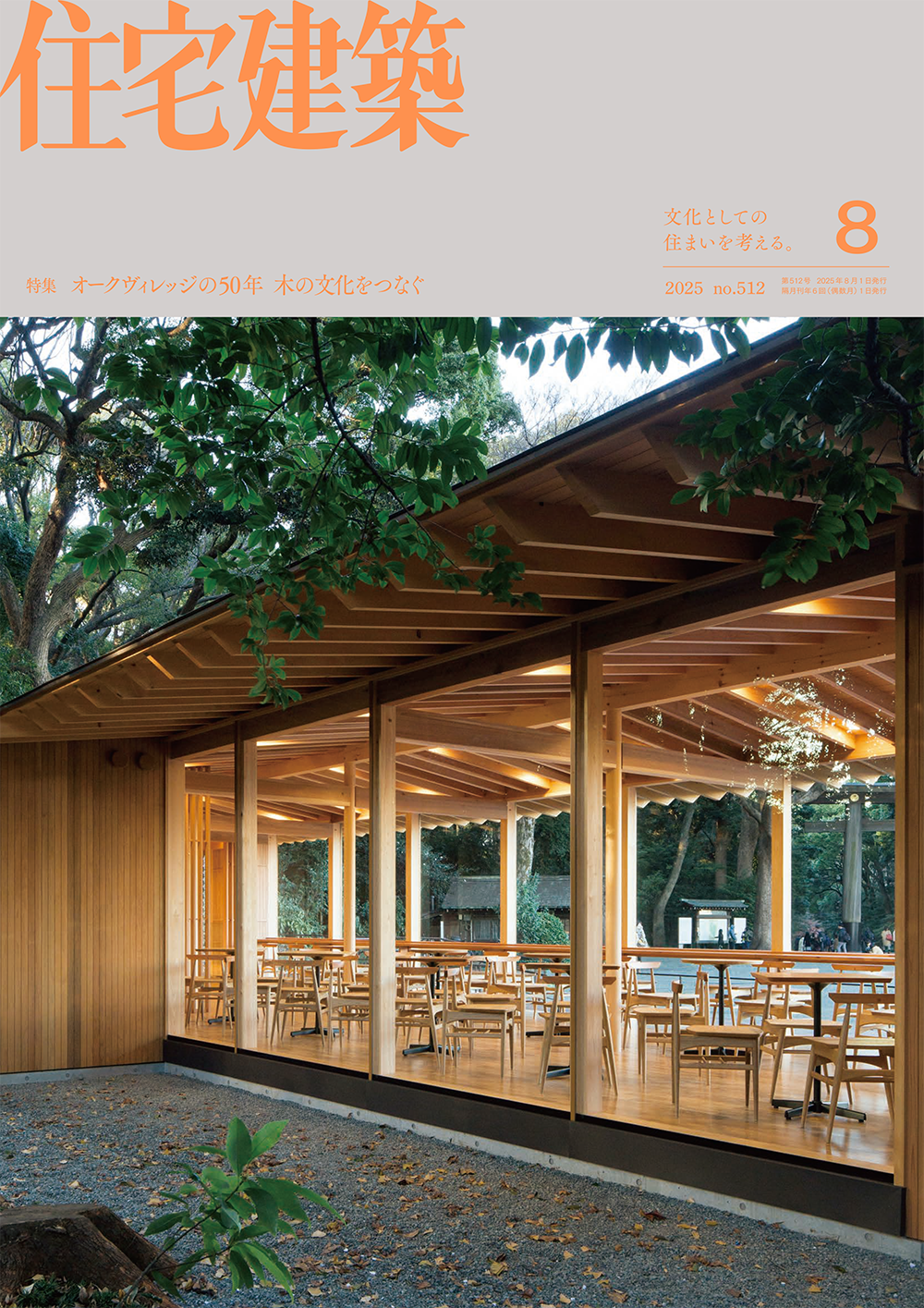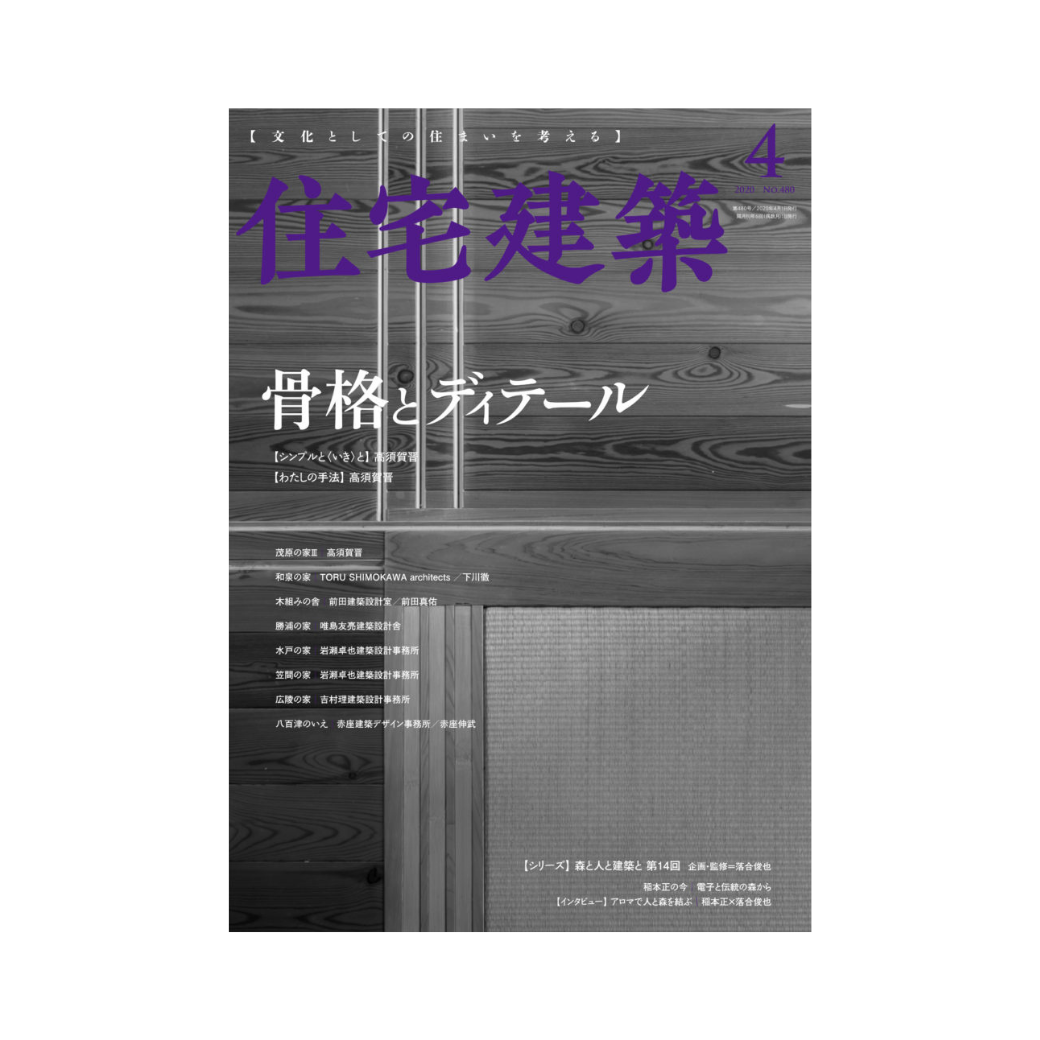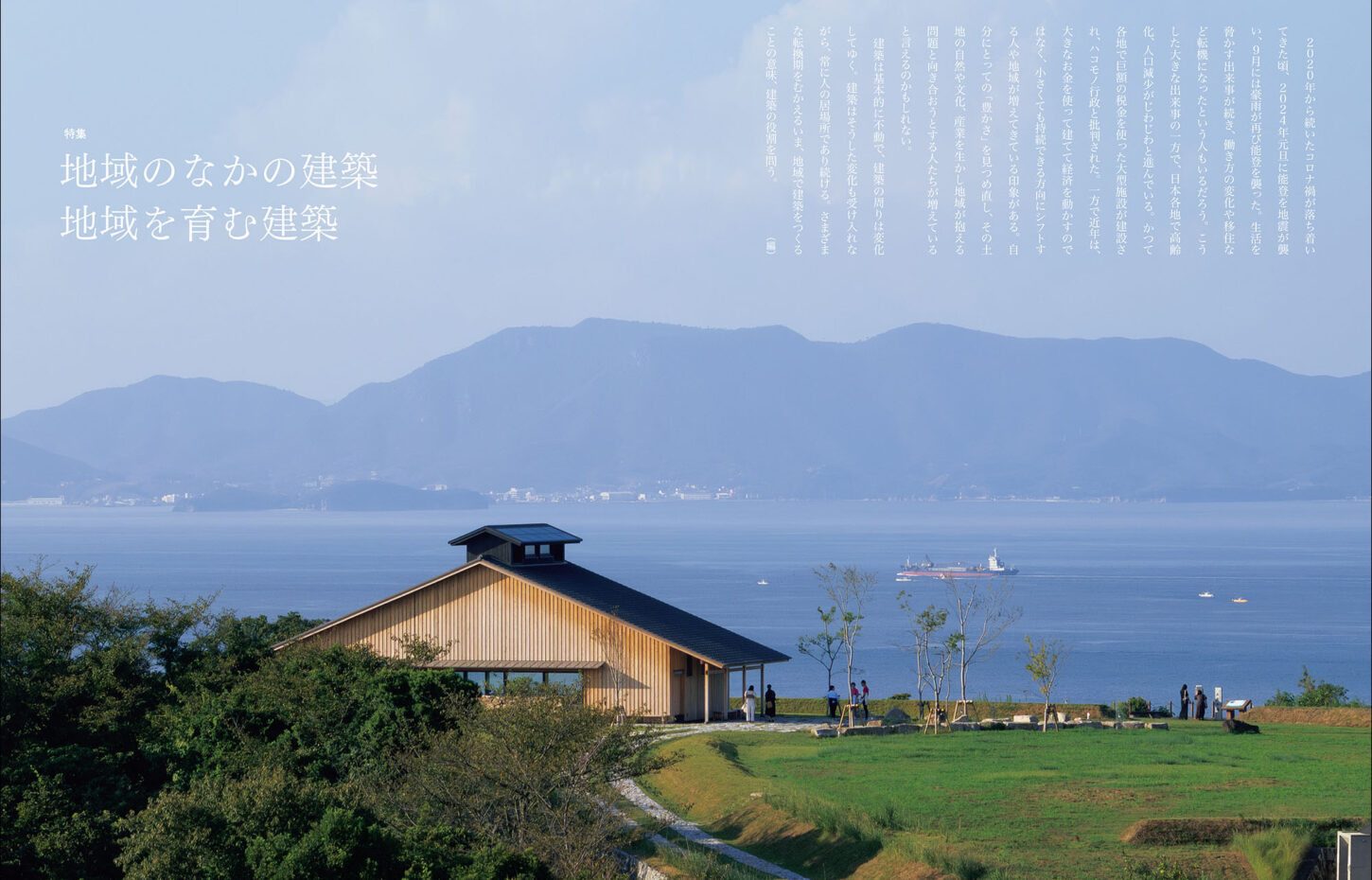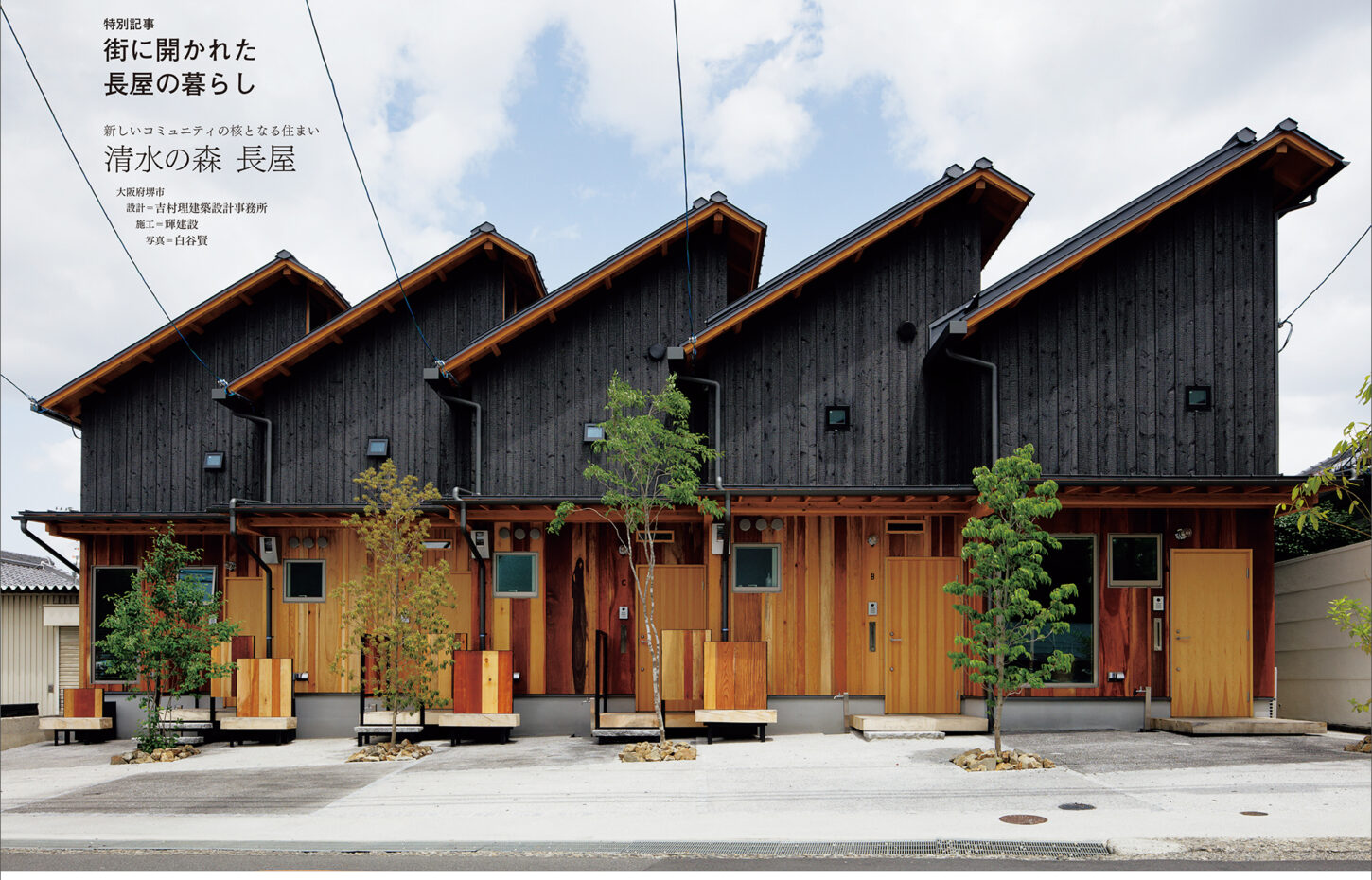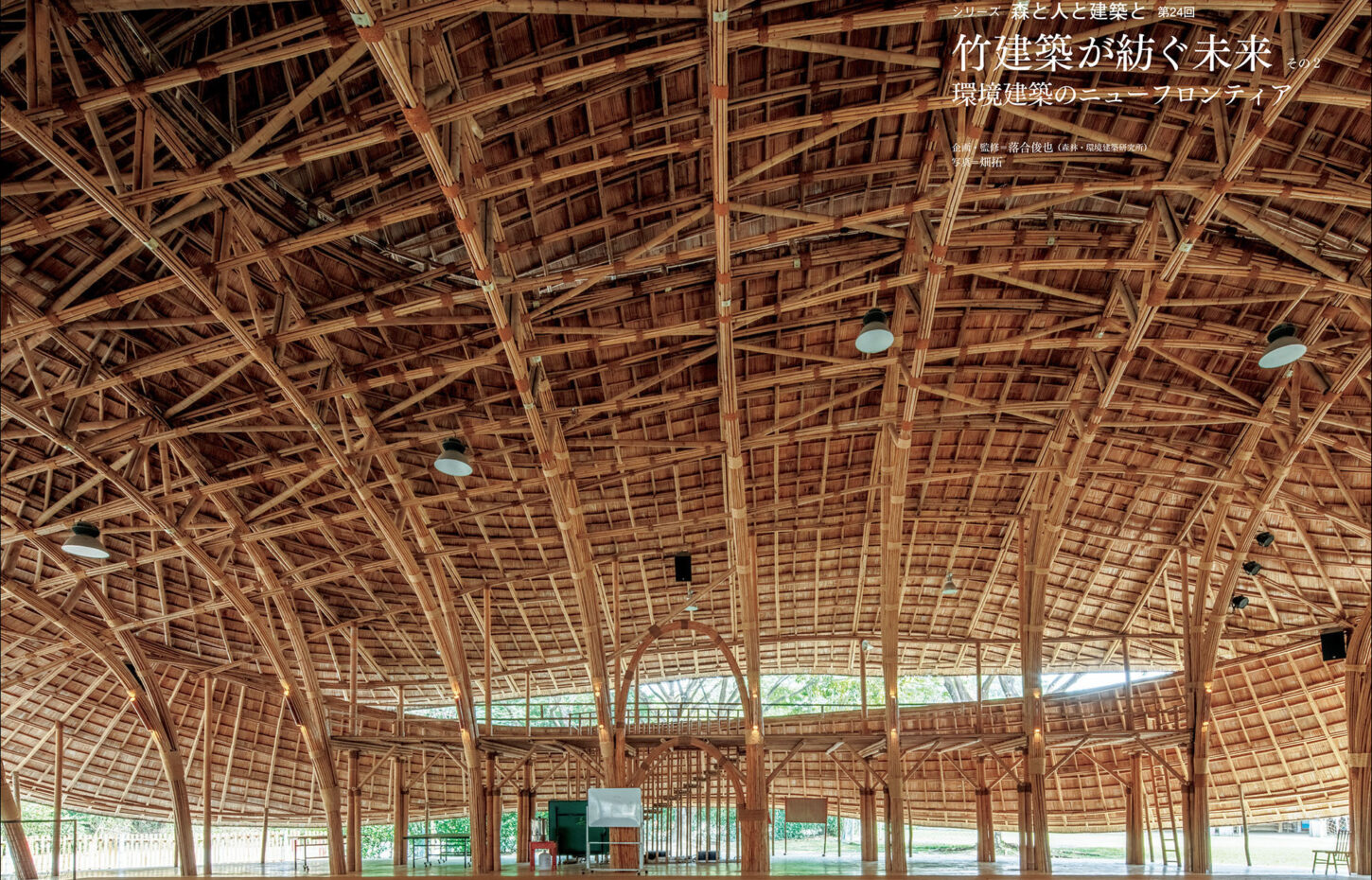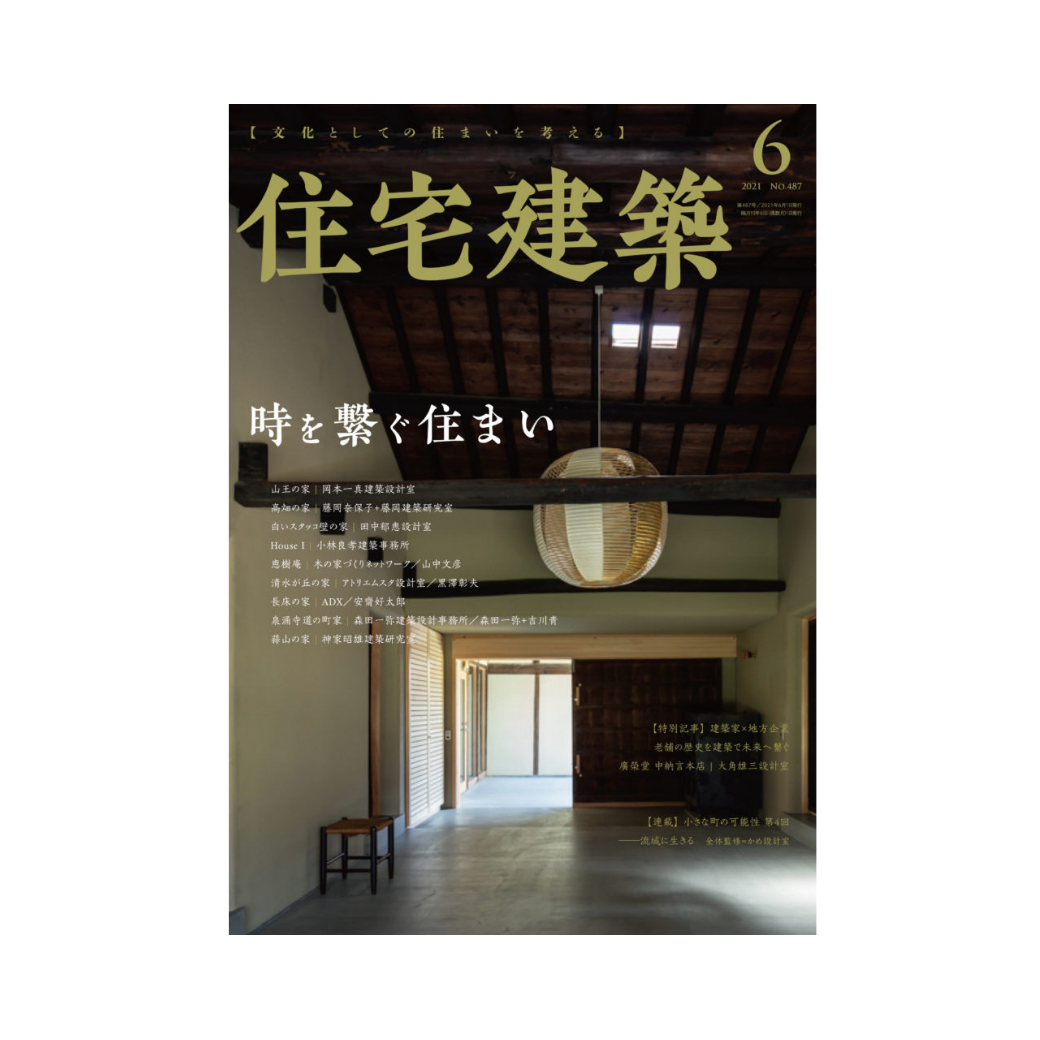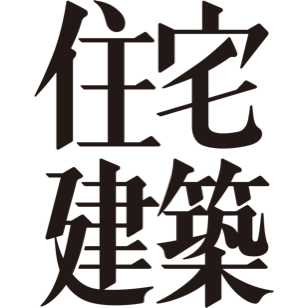
【8月号書評】『神戸——戦災と震災』(村上しほり 著/ちくま新書)
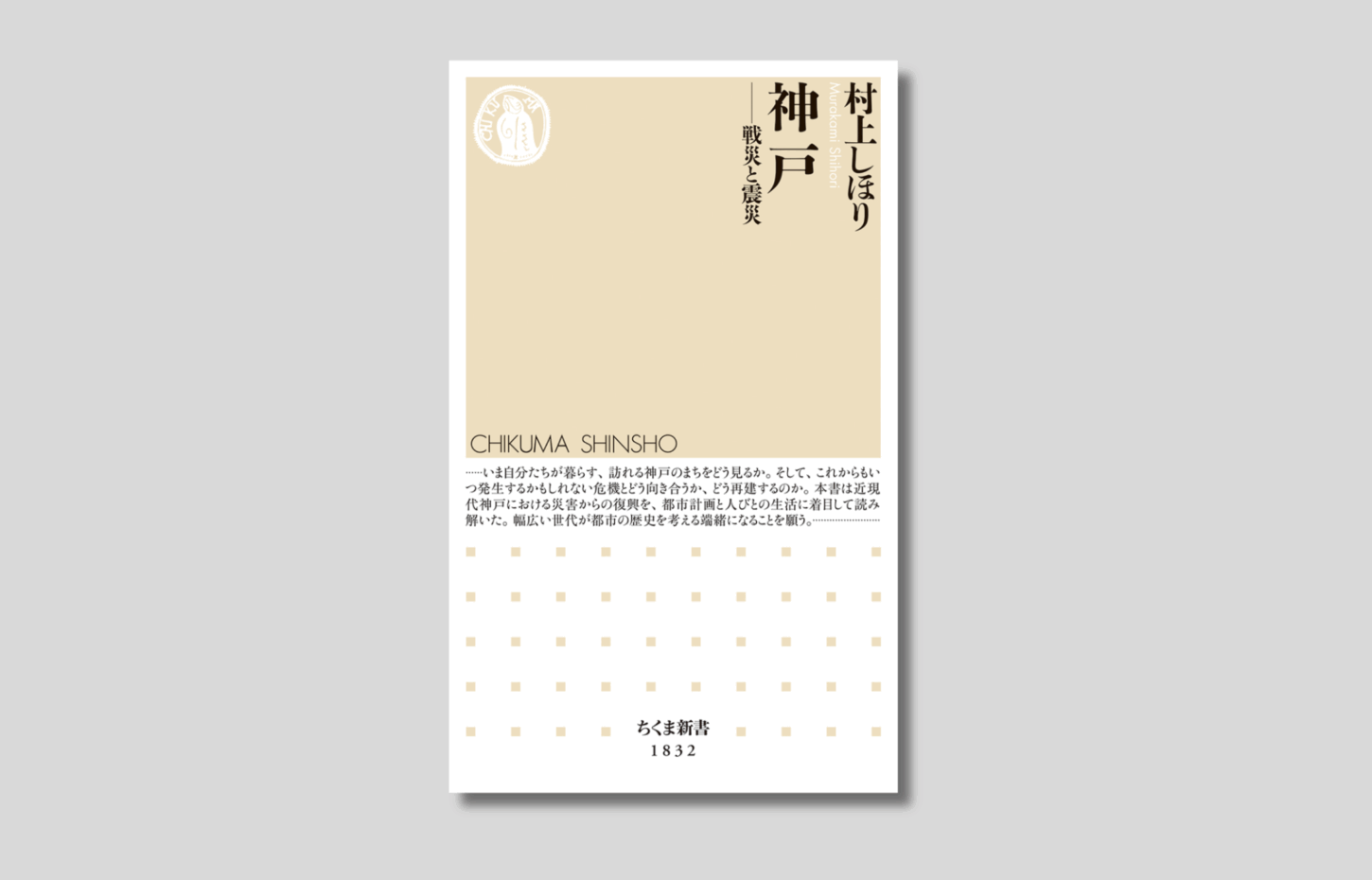
『神戸——戦災と震災』
村上しほり 著
ちくま新書/2024年/376頁/新書判/1,320円(税込)
災害とその積み重ねからみる「神戸」
評者:石榑督和(関西学院大学准教授)
暮らしたり訪れたりしてよく知っていると思っているまちが、違って見えてくるような都市史研究は魅力的だ。本書を通して、読者は昨日まで見えなかったものが、まちの特徴として見えてくるだろう。
神戸の次期マスタープラン策定のために近年行われたアンケート調査で、神戸の地元の人が神戸のまちの魅力として上位に挙げたのは「海と山に囲まれた自然豊かな環境」「夜景の美しさ」「都会でありながら田舎・里山もあるまち」「オシャレ」であった。著者の村上しほりは、この結果に、地元の人間が答えているにもかかわらず、視覚的な魅力ばかりが挙げられ、結果として神戸らしさというより日本中どこにでもあるようなまちの魅力になってしまっている、と危機感を示している。「明治から現代までの神戸の都市史をひとつながりに捉え、罹災からの復興によって生まれた神戸」を深く知っていくことで、見た目の美しさだけでない、つらさや苦しみを抱えた神戸をも愛おしく思える可能性を開くことを、本書は目指している。
災害と復興から描く神戸
今年は神戸にとってメモリアルな年だ。阪神・淡路大震災から30年、第二次世界大戦の終戦からは80年の年である。本書の主題はこの2つの災害とそこからの復興からみる神戸の都市史である。さらに1938年の阪神大水害も含めると、20世紀に神戸は3度の大きな災害にあっては復興をしてきたまちである。本書は3部構成。第1部は「近代」として開港から阪神大水害からの復興までを、第2部は「1945〜1995」として終戦から阪神・淡路大震災前を、第3部「1995〜2025」は震災と復興、そして現在までを描いている。
ところで、非常に個人的なことで恐縮だが、私は4年前に東京から阪神間へ引っ越した。阪神間で暮らすようになって、私が生活者として強く感じたのは、古い建物があまり無いことである。日々いたるところで開発が続く東京と比べても、古い建物が少ないように感じる。もうひとつ、東京との違いで言えば山が常に見えて身近なこと、少し自転車に乗れば海にも川にも触れられることであった。この2つの実感は本書の扱う災害に直結する。前者の印象は阪神・淡路大震災による被災によって木造の「普通」の建物が失われたことによるものであり、後者の印象は治水事業を実施しなければ水害へ繋がる可能性があるものである。
明治初期から形成が始まった港町としての神戸が大きく壊れた1938年の阪神大水害、そこから復興しつつあったまちをまた破壊したのは戦災(建物疎開と空襲)であり、さらにそこから復興したまちや戦災を受けなかったまちの再整備が進む途上で神戸を崩したのが阪神・淡路大震災であった。ただ本書はこの3つの災害と復興を一様に扱ってはいない。むしろ著者と各災害との距離感の違いが現れているのが特徴であろう。
日本の近現代史と神戸の都市史
著者の村上しほりは1987年生まれの神戸育ちである。「いま思うと私たちの青年期は、阪神・淡路大震災の影響を大きく受けた、震災復興下の神戸」にあり、「聞く対象として、阪神・淡路大震災はあり続けた」という。それに対して、震災の50年前の戦災とそこからの都市再建やその後震災までに形成された神戸のまちを「近くて遠い存在」と感じ、研究対象として考え始めたのが、著者が神戸の都市史研究をスタートするきっかけとなったという。
本書のハイライトはまさにその部分、第2部「1945〜1995」の前半である。戦時下の神戸の生活と被災(第3章)、戦後に無名の人びとが群れることでつくり出した闇市とその整理過程で生まれた商業空間(第4章)、そして同時期に行われた連合国軍による占領(第5章)を描いた3つの章である。
本書は一貫して全国的な法制度の整備や変化を簡潔におさえたうえで、神戸の個別的な都市計画事業について記述している。ただそれだけではない。まちをつくる骨格としての都市計画を捉えながら、そのなかで営まれる人びとの具体的な暮らしを聞き取りから明らかにして伝えている。その解像度の高さは本書のハイライトの3つの章では際立ち、神戸を生きてきた人びとの人生の一部を追体験するようでもある。
神戸に限らず戦前と戦後の都市史は断絶として描かれることが多い。しかし、実際には市民生活は連続しており、焼け跡に立ち上がった世界がまったく新しく生まれたわけではないことを教えてくれる。そしてその生活に戦災や占領がどのように影響を与えていたのかが示されている。
2010年代以降、これまで歴史の対象にあまりなってこなかった「戦後の都市空間」が、歴史研究の対象となり、日本の戦後都市史が盛んに描かれてきた。著者の村上はそうした研究を牽引してきた研究者の一人であるが、他の戦後都市史研究と村上の研究を比べたときに特筆すべき点は、闇市として機能した露店やマーケット、バラック街の形成を明らかにするだけでなく、同時代の連合国軍の占領についても明らかにし、市民生活との関係を明らかにしてきた点にある。戦後都市史研究の成果とは別に、近年、日本における占領の空間史研究も大きな進展を見せている(大場修 編著『占領下日本の地方都市―接収された住宅・建築と都市空間―』思文閣出版、2021年)。神戸をのぞいて、この両者を解像度高く明らかにし、都市の歴史が書かれた場所はほとんどない。
震災の記録と記憶を繋ぐこと
村上は自身のことを「都市史研究者」であり「アーキビスト」であるとしている。戦時下から占領復興期の神戸を描いたのが「都市史研究者」としての側面が強く現れた部分だとすれば、本書での阪神・淡路大震災とそこからの復興への向き合い方は「アーキビスト」としての側面が強いと感じた。アーキビストとは、歴史資料の材料となる文献や遺物を、特定のアーカイブズの設置目的に適うかどうか判断し、選択と整理保存を行う専門職である。村上は神戸市の公文書専門職のひとりとして神戸市歴史公文書館設置(2026年度開館予定)の準備を進めている。本書の第3部では阪神・淡路大震災後の神戸の歴史とともに、それに関わる記録がどのように収集され、繋がれてきたか、さらに今まさに神戸市が進めつつある神戸の記録を残す活動の展望を教えてくれる。
震災に関わる出来事について実体験を語る「語り部」の活動がある。阪神・淡路大震災を経験した語り部も発災から30年が経ち高齢化している。その活動を継ぐために、実際には出来事を経験していない若い世代の語り部を育成する動きが見られるという。その活動は「ストーリーテリングによる意味の伝承にも近いように見える」と村上は言う。分析・検証・考察にさらされるものではなく、聞き手の感情を揺さぶる「語り」が引用される「出来事の伝え方」に、村上は必ずしも賛成できない立場であるように私には読めた。村上の都市の過去への向き合い方の姿勢を示している。過去の出来事をそれを経験した当事者の率直な「語り」で伝えるのではなく、繰り返し語られる際に被災や復興の「ストーリー」として映える「語り」が強調され、さらには非当事者によって「語り継がれる」ことによって、過去が歪められていく可能性があることに筆者は危機感を抱いているのではないか、と私は感じた。
他方で「語り部」の方々の間で活動を通じて連帯が生まれていくこと自体も地域にとっては重要なことであると、その意味を見出している。人のライフスパンを超えて地域の出来事を「伝えていく」ことの複雑さを考えさせられた。
2025年4月13日に大阪・関西万博が開幕し、兵庫でも関連して多くの「ひょうごフィールドパビリオン」が展開され、万博に訪れた人が合わせて兵庫の文化と歴史を知ることができる体験プログラムが組まれている。今年、本書を持って神戸を訪れ、変化する新たな「神戸」とその歴史を見直す体験をしてみるのはいかがだろうか。きっとこれまで知らなかった神戸を知ることができるはずだ。
石榑督和(いしぐれ・まさかず)
1986年 岐阜県に生まれる。2014年 明治大学大学院博士後期課程修了。明治大学助教、東京理科大学助教などを経て、2021年より関西学院大学建築学部准教授。2020年『戦後東京と闇市』、2021年『津波のあいだ、生きられた村』(共著)で日本建築学会著作賞を受賞。共著に『シェア空間の設計手法』『PUBLIC PRODUCE「公共的空間」をつくる7つの事例』『日本のまちで屋台が踊る』などがある。