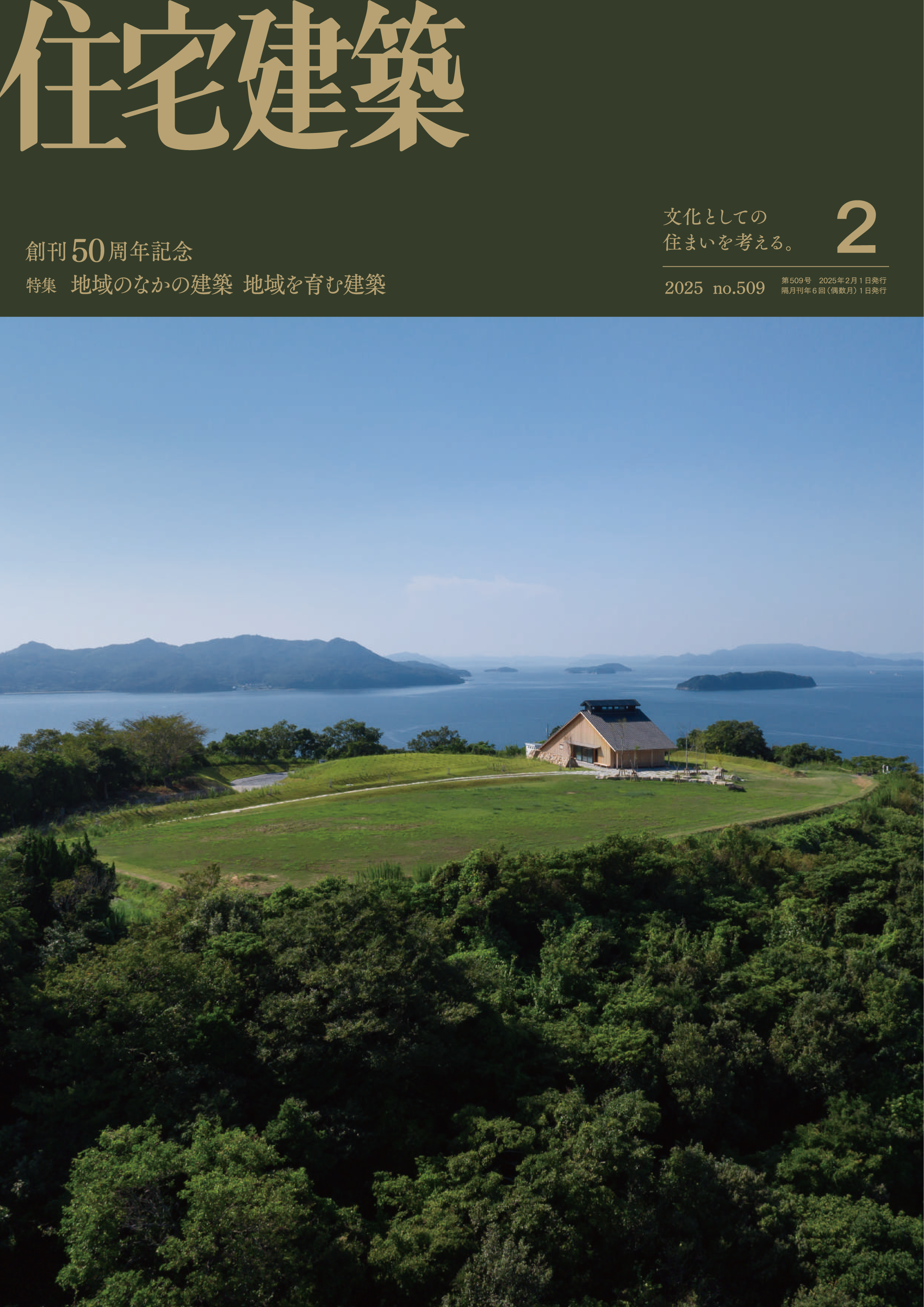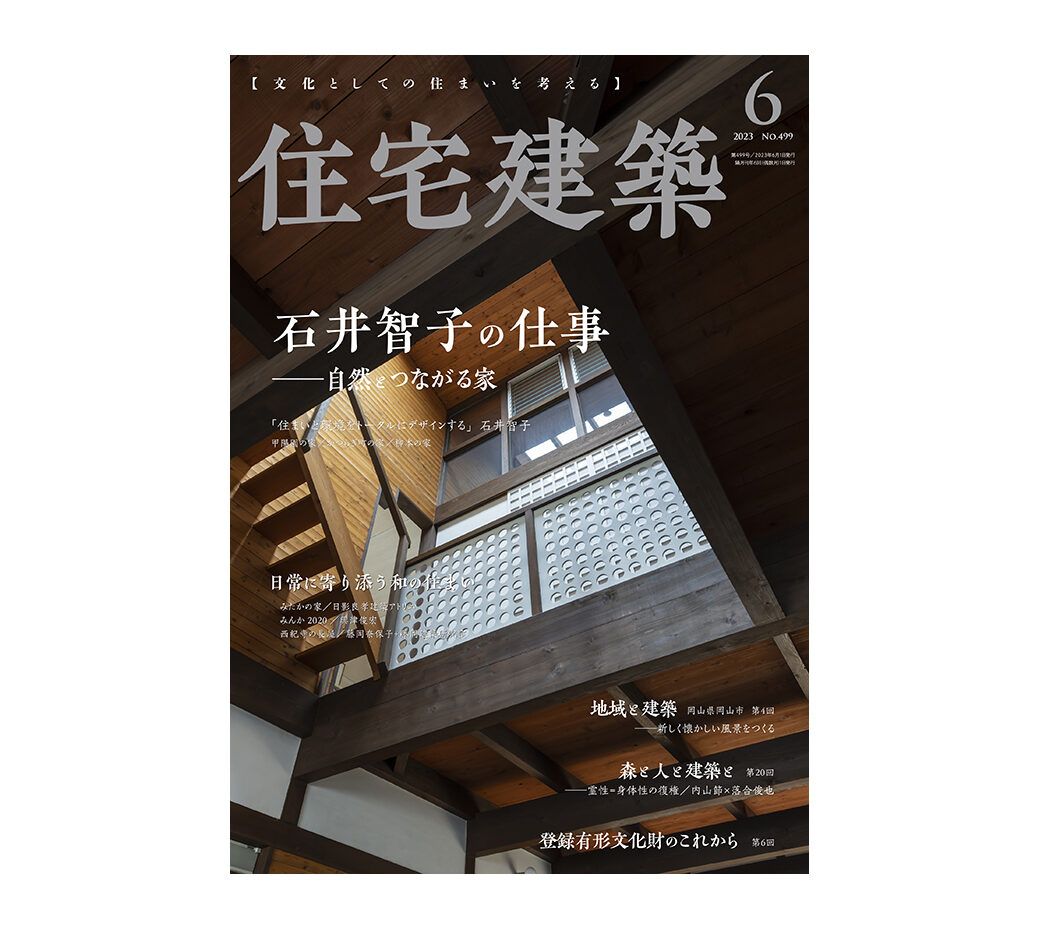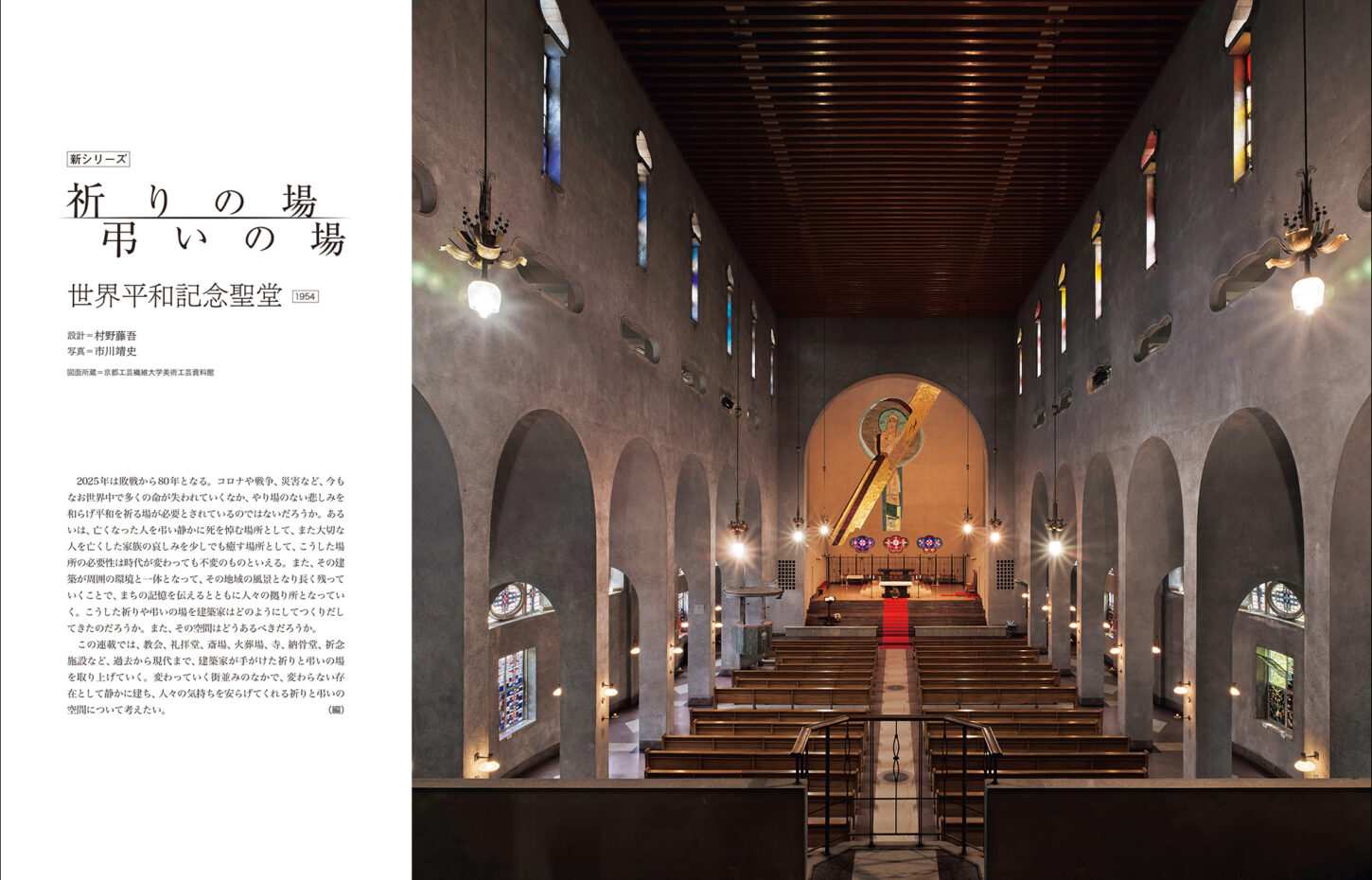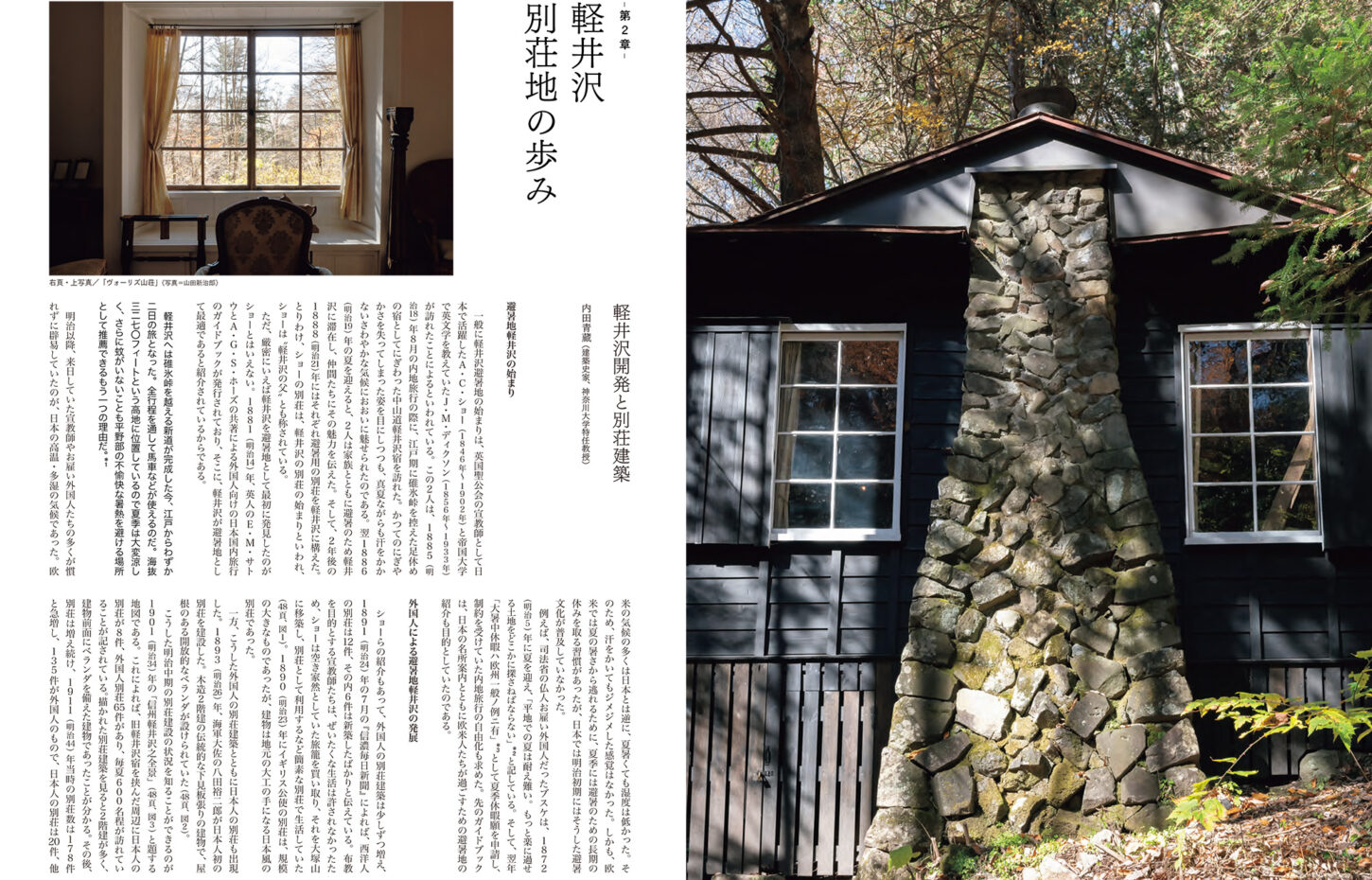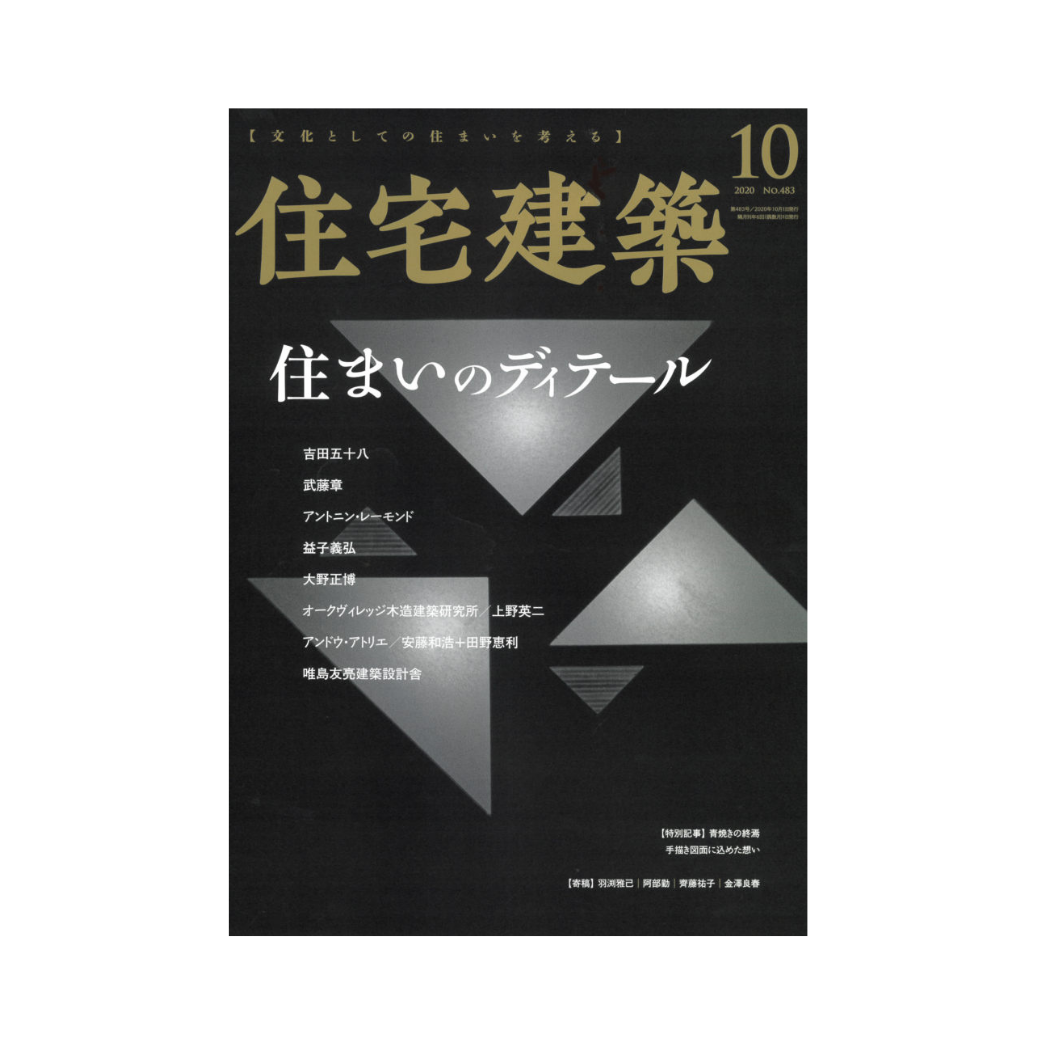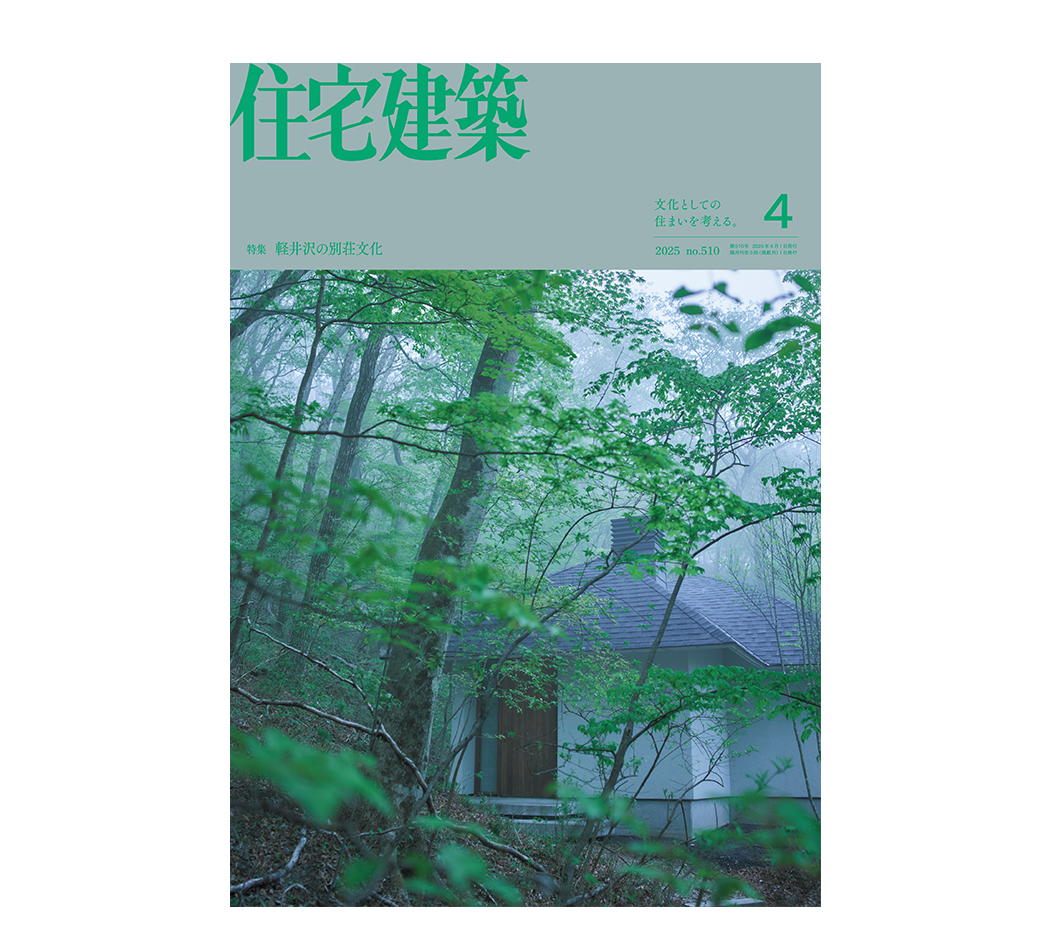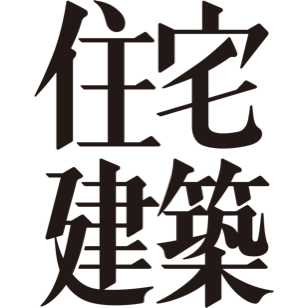
【2月号書評】『都市と緑の人類史』(ベン・ウィルソン 著、森夏樹 訳/青土社)
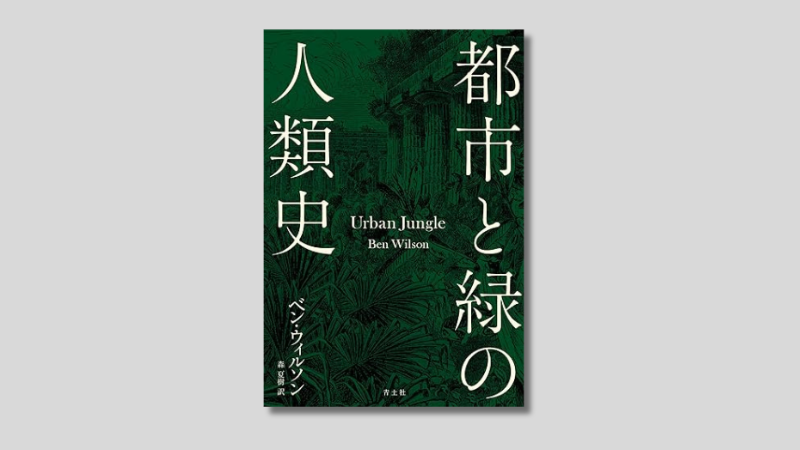
『都市と緑の人類史』
ベン・ウィルソン 著、森夏樹 訳
青土社/2023年/368頁/四六判/3,960円(税込)
都市を耕し、生態系に編み込む
評者:山田貴宏(ビオフォルム環境デザイン室)
資源の枯渇と環境容量の限界の時代を迎え、私たちは今後の文明観をどう描いたらいいか、さまざまな逡巡と試行錯誤が続いている。とくに都市部では、エネルギー、水や食料の消費とその廃棄、という一方通行的な仕組みのなかで、「限界都市」を迎えている。太陽のエネルギーを原資として成立しているこの地球上では、それを固定化してくれる唯一の存在は(原始的な生命体は別として)、「植物」である。資源と栄養の循環性を鑑みると、私たちは好むと好まざるとに関わらず、基本となるのは、植物およびそれを取り巻く生態系の仕組みであり、それを下敷きにしながら今後の文明を構想する必要がある。2050年には世界の都市人口が約7割になるそうだ。とすると、都市における植物との関係性を根本的に見直し、その構造をリフォームしていかなければ、ますます破綻していくことになる。
本書は、イギリスの歴史学者であるベン・ウィルソンが古今東西の豊富な事例を具に調べ上げながら、都市における植物および生命系の仕組みがどう成り立ち、変化していったか、ということを丁寧に数多く紹介している。技術者ではないのでこれからの解決すべき課題に対して具体的な技術論を展開しているわけではないが、この「文明史」を辿ることで、これから目指すべきイメージを巧みに浮かび上がらせている。
夫々の章立ては「都市の拡大と田園のせめぎ合い」「管理された都市公園の成立とその変容」「都市内の野生性」「都市内外の樹木の効用」「都市内生態系機能(とくに水系)の復活」「都市内食糧生産と循環」「都市の生物多様性と共生」という構成になっている。読後すべてを俯瞰すると、散らかっていた引き出しの中が綺麗に整理されたような感覚がある。全体に通底しているのは「都市を野生化する」というややラジカルにも捉えられる態度であり、著者はそこからこれからの都市像を提起している。
本書の中でも書かれているが、都市における植物の役割は、歴史的には「特権階級のための囲われた庭園」から「大衆のための公衆衛生の視点を持った公園」へと民主化され、拡大し進化してきた。それが現代は環境の時代に導かれ、さらに多面的な環境機能を伴いながら都市に多様な手法とスケールで緑が増えてきている。
かつての単なる「田園を模倣した緑地」から、現在は「都市内緑地が生物多様性を備えた仕組み」へとシフトしてきているわけである。
そうした流れから、昨今の建築においても緑を屋上や外壁に纏っているものがあり、都市開発があれば、その足元のありとあらゆるところにも緑が小綺麗に植えられている。こうした状況は歓迎すべきだが、しかしながら相変わらず「管理」された自然の様相を呈し、都市内における自然生態系は人間がコントロールすべきもの、という感じもある。管理された「量」から、その多様な役割を実装する「質」について、もう少し踏み込んだ議論をし、計画していくことがまだまだ必要なのではないか。
生態系がもつ多様な機能は、都市内気候の緩和や都市内循環の実現など、いわゆる「生態系サービス」と言われていて、そうした視点は生物多様性を伴いながら都市環境を改善していく仕組みに接続していくだろう。従来の都市インフラのようなハードエンジニアリングによる都市の運営から、グリーンインフラのように、生態系のもつ機能を組み込んだソフトエンジニアリングの仕組みも考慮されるようになってきたわけである。
その芽は実は、すでに1960年代から模索され始めていて、ここでは詳述しないが、例えば、イアン・マクハーグの「エコロジカルプランニング」論やニューアルケミー研究所のトッド博士らによる「バイオシェルター」の提案に結実されている。バイオシェルターは「生物学と建築、都市の統合」という魅力的なテーマを掲げ、あくまで生命の仕組みが我々人間の行うデザインの礎にある、という姿勢を貫いている。今でもなお未来を感じる技術的思想であり、注目に値する。
こうした文脈の先に、昨今は「リジェネラティブ」「ネイチャーポジティブ」「サーキュラー」などのキーワードが語られ、環境への負荷「低減」のみならず、むしろ人の行為が生態系を豊かにしていくような仕組みを構築していこうという能動的な動きもある。環境倫理の追求やディープエコロジーなどの思想が、環境問題への技術的対処の裏側で静かに思索されてきていたが、その胎動していたものが近年徐々に表現されるようになってきている。こうした視点をもつことは都市構造を再考するうえでも非常に重要である。
ただし、一方では相変わらず生態系を客体的に「サービスを提供してくれるもの」という文脈で認識することにはいささか違和感があるのも正直なところである。こうした動きは生命を見つめる眼差しを常に保持しておかないと、機能と数字で語る機械的な環境主義に取り込まれ、それは市場主義と結びつき、記号化して消費されてしまう危険性もある。例えは多少違うかもしれないが、かつて1991年にアメリカ・アリゾナの地で「バイオスフィア2」という巨大な温室の中に閉鎖系のミニ生態系を再現する、というプロジェクトがあった。生態系の仕組みを商業的に利用する目的がその先にあったのだろうと推察するが、失敗だったと私は理解している。生態系の仕組みはそう単純ではないし、むしろ荒々しい側面も多々ある。自然を「利用する」ということに我々は常に謙虚であるべきだろう。
さて、本書の中で語られている「都市を野生化する」という思考に立ち戻ってみる。「野生化」といういささか強い言葉を使っているのは著者がイギリスの気候風土の原体験があるからか。日本を含むアジアモンスーン地域においては、「野生化」はともすると「脅威」であり、人がいなくなれば簡単に都市は森林に戻る。自然の圧力は強い。都市というものには自然を駆逐しているイメージがあるが、本当は自然の圧力に対して必死に抵抗しているのかもしれない。生態系は各要素が参加している「相互作用」の積み重ねがその安定性に繋がっているわけだから、植物や生態系を客体化するのではなく、どちらかというと生態系の網目に都市を編み込む作業が必要であり、そのためには人と自然の相互作用が常に存在していることが重要である。その最たるものが、言ってみれば「里山」ではないだろうか。里山を簡単に表現することは難しいし、それを都市と結びつけるイメージは湧かないかもしれない。里山は自然と人の生業の接点、エッジであり、そこに適度な撹乱があり、それゆえ多様性が息づいているという場所である。自然を都市に「引き入れて野生化」するよりも、イメージとしてはこうした相互作用的な「里山」的な仕組みを手本に都市をリフォームしていくことを構想したい。ちなみに東京においては、江戸時代にはいわゆる公園はなかったものの、大名屋敷の敷地内には庭が豊かに設らえられており、そこには自給的な菜園も備えていた。現代でも高密度と言われている23区内でも各住宅の庭にはそれなりに植物が植わっているし、都市内農地もまだ散見でき、よく見ると案外植物の量はあるように思える。近代的な公園のようなまとまった緑地をつくる構造とは別に、食べられる緑の小規模分散かつ広域的な配置、という仕組みがすでに元々あり、その構造がまだ残っているといえよう。これは欧米の都市の構造の成り立ちといささか違って、アジア的な風景である。
また、「農」というと畑や田んぼがイメージされるが、それのみならず、海や川など水系の豊かさも含んだ「農」的仕組みにおいては、栄養、エネルギー、食はすべて繋がっている。もとより都市にはたくさんのエネルギーと食料、すなわち栄養が流れ込んでいて、その消費と廃棄たるや膨大であるが、それを都市内での農的な循環型の仕組みにしていくことで、汚染と資源の枯渇を解消していくポテンシャルが実は都市には自ずと備わっている。
以上を俯瞰してくると、都市と緑の関係の未来像として「都市を耕す」という、人が関与する仕組みが実は都市の生物多様性や生態系の構築に大きく寄与し、そうしたハイブリッドな視点が今後の都市における緑のあり方の可能性を示しているかもしれない。
最後に。本書が示すように植物や生物という要素は非常に大事であるが、それと合わせて、水や風の流れも都市環境の重要な要素であり、それがないと緑もいきてこない。統合的な視点で、都市環境の生態系を取り戻す方法を考えていきたい。
山田貴宏(やまだ・たかひろ)
1992年 早稲田大学理工学部建築学科都市環境工学専修修了。1992年~1999年 清水建設勤務。1999年~2005年 長谷川敬アトリエ勤務。2005年 ビオフォルム環境デザイン室設立。伝統的な木の建築などを基本とした地産地消の建築/環境設計を行う。