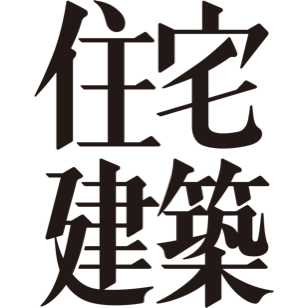
【2024年12月号書評】『世界への信頼と希望、そして愛 アーレント『活動的生』から考える』(林大地 著/みすず書房)

『世界への信頼と希望、そして愛 アーレント『活動的生』から考える』
著=林大地
みすず書房/2023年/424頁/四六判
「若くて、力のある書物」
評者:島田潤一郎(夏葉社代表)
私的なことからはじめて恐縮だが、2009年からひとりで出版社を経営している。
多少でも本のことに興味のあるひとは、ぼくが出版社の社主だと知ると、口を揃えて、「たいへんでしょう」と言う。
いいえ、そんなことないですよ、と返すと、相手は「やっぱり、好きなことだからでしょうね」といい、「好きなことを仕事にできるっていいですね」と続けて、最後に、「がんばってください」と言う。
どれも、そんなに当たっていない。けれど、そんなに悪い気持ちもしない。本を好きなひとが、良かれと思って口にしていることだからだ。
いうまでもなく、この15年間で、出版業界は大きくかわった。業界全体の売上は年々下がり、書店の数も激減した。本をとりまくニュースのほとんどは悪いものばかりだ。
「紙の本」で大儲けしようと目論むなんて、並外れた山師か、「経験者」以外にいないのではないか、と思う。この業界にはまだベストセラーを世に出した「経験者」がたくさんいるから(編集者の場合、彼らのほとんどは管理職である)、売上を「取り戻そう」などという発想が出てくる。が、ぼくのような新米経営者はそんなことを露ほども思わない。それよりも、いい本をつくりたい、と思う。
らくな商売ではない。けれど、たいへんだ、と思ったことはないし、「紙の本」に未来がないと思ったこともない。一度たりとも。
たしかに、たくさんの読者がいなくなった。けれど、それは知り合いの書店主がいみじくもいったように、「読書を第二、第三の趣味とするようなひとたちが書店に来なくなった」ということなのであり、その彼がいったとおりにここに記すと、「好きな作家の新作が出ても、とりあえず文庫になるまで待つか」というくらいに本を好きな読者がいなくなったということに過ぎない。それはより具体的にいえば、角川文庫、講談社文庫、文春文庫といった、かつてはよく売れていた文庫の売上が激減したということだ。あくまでも、その店主の店の場合だけれど。
なにをいいたいのかというと、読書を第一の趣味とするようなひとたちは、すくなくともぼくが出版社を経営するこの15年のあいだは、まったく減っていない。そればかりか、印象的には、若干増えているように思う。
なぜか。
それはひとことでいえば、本という「物」にたいする信頼なのではないか、と思う。
今年の春に知人に勧められて読んだ林大地さんの『世界への信頼と希望、そして愛』のなかの一節を、ぼくはどれだけ多くのひとに聞かせただろうか。書店の棚の前で。トークイベントで。SNSのライブ放送で。
ぼくは、「とにかく聞いてください」といって、一言一句聞き漏らさないでください、というように、次のくだりを大きな声で読むのである。
では「信頼」と「希望」とは何か。本書では、アーレントのテクストに依拠しつつ、これら二つの言葉を、以下のように定義する。(一)世界への信頼とは、世界はこれからの長きにわたって続いてゆくのだと感じられるところに生まれるものである。(二)世界への希望とは、世界はこれからも絶えず新たにされてゆくのだと感じられるところに生まれるものである。言いかえれば、(一)世界は「物」の「持続性」を通じて「存続」するがゆえに、私たちは世界にたいして「信頼」を抱くことができるのであり、(二)世界は「人間」の「出生性」を通じて「新生」するがゆえに、私たちは世界にたいして「希望」を抱くことができるのである。
相手がどのような反応をしめしているか、確認する余裕がない。なぜなら、自分にとって大切なことを話すときは、それがたとえ朗読であったとしても、とても緊張するからだ。と同時に、この一文を読んでいると、毎回気持ちが高ぶるからでもある。何回読んでも、そうだ、そのとおりだ、と思う。
ぼくは、この本にたびたび出てくる「物」の「持続性」という話を、「本」の「持続性」と読みかえて読んでいる。 それは、装丁家の和田誠さんが『装丁物語』(中公文庫)で次のように書いていることととても似ている。
書籍はベルトコンベアで流れ出てくるものではありませんし、読んだら捨てちゃうというもんじゃない。そういう本もあるだろうけど、書籍というものはたいがい読まれたあと書架に置かれ、いい本なら繰り返し手に取られ、もしかしたら孫の代まで受け継がれるものです。ティッシュペーパーの箱とは根本的に違う。
和田誠さんは、「本」は消費財ではないといっている。それは言葉をかえれば、日給、月給を得るためにつくられた、単なる「労働の産物」ではないということであり、もっと持続する可能性を秘めた「物」だということである。
ぼくは和田さんのこの言葉を何度も思い出し、自分を鼓舞するように本をつくってきた。それはよろこびというよりも、責任のようなものであり、お金のためだけにくだらないものは絶対につくってはいけない、と事あるごとに自分を戒めてきた。
林さんは、というか、アーレントは、その「物」の「持続性」を、「世界への信頼」と呼ぶのである。
和田誠さんは2019年に83歳で亡くなった。が、和田さんが手がけたたくさんの本はいまも書店と図書館、そしてひとびとの書斎のなかに今もある。当たり前だが、和田さんが亡くなったからといって、それらの本もいっしょに消えてなくなるわけではない。和田さんがつくった本は、和田さんの人生よりも長くこの世に残る。
これを読んでいるひとのなかには、そんなことはあたりまえだ、と思うひともいるかもしれない。けれど、ドイツ系ユダヤ人として、20世紀のもっとも暗い時代を生きたアーレントにとって、それは決してあたりまえのことではなかった。
もし想起や物化がなかったら、〔…〕生き生きとなされたこと、語られた言葉、考えられた思想は、行為、言論、思考といった営みがその終わりを迎えるやいなや、跡形もなく消え去ることになるだろう。あたかもそれらは存在したことなどなかったように見えるだろう。(ハンナ・アーレント『活動的生』、森一郎訳)
私たちは、世界のあらゆるひとびとは、たったひとりの例外もなく、死から免れることはできない。どんなに願っても、不死の願いをかなえることはできない。
けれど、わたしたちは物をつくることができる。言葉を紙に書いたり、印刷したりして、だれかに送ったり、あるいは、自室のだれにも見られないところに、そっとしまいこむことができる。世界はそうした「物」にあふれているのであり、そのありふれた事実が、わたしたちがこの世から去っても、世界が続いていくということを雄弁に伝える。
もちろん、その世界がいまのまま、現状維持でいいというわけではない。世界は昨日よりもよい世界であるべきである。
本書のテーマは「世界への信頼と希望、そして愛」であるが、「信頼」が「物」の「持続性」にあるとすれば、「希望」は次のように述べられる。
世界はしかし、まったく老いることなく、生き生きとしたままそこに在る。むしろ世界は若返ってさえいる。これはなぜか。それは『活動的生』の議論に即していえば、この世界に絶えず新たな子どもが生まれ落ちているからであり、その子どもたちが彼らの生まれ持った新しさでもって、この世界を絶えず新たによみがえらせているからである。
ぼくはこの本を読みながら、何度も、子どもたちが生まれてきたときのことを思い出した。
長男も、長女も帝王切開によって生まれ、長男のときは、その病院の考えによって、妻のお腹にメスが入る瞬間にも立ちあった。
医者は妻の腹部に手を入れ、そのなかから血まみれの赤子を取り出し、ぼくに手渡した。
それは紛うことなき「希望」であり、ぼくは、自分をとりまく世界がまたたく間にあたらしくなっていくという経験を、そのときにしたのである。
去年、たまたまアーレントの『イェルサレムのアイヒマン』(みすず書房、大久保和郎訳)を読んだが、そのときは最後まで、難解であるという印象を拭うことができなかった。
本書が論じている『活動的生』ももしかしたら、同じくらい難しいのかもしれない。
けれど、林大地さんという若い研究者が紹介するアーレントは驚くほどにみずみずしく、ここには読み手を奮い立たせるような思考の力、あるいは文章の力がある。
そこにはおそらく、林さんのアーレントへの愛、そして、世界への愛も深くかかわっているのだろう。
物をつくるすべてのひとに読んでもらいたい好著である。
島田潤一郎(しまだ・じゅんいちろう)
1976年 高知県に生まれる。東京育ち。日本大学商学部会計学科卒業。大学卒業後、アルバイトや派遣社員をしながら小説家を目指していたが挫折。2009年9月に33歳で夏葉社を起業。ひとり出版社のさきがけとなり、今年で15周年を迎える。著書に『あしたから出版社』(ちくま文庫)、『古くてあたらしい仕事』(新著文庫)、『長い読書』(みすず書房)など。






